■『ブラタモリ #15 出雲』
【ブログ内関連記事】
![]() 出雲 縁結びの旅へ!@歴史秘話ヒストリア
出雲 縁結びの旅へ!@歴史秘話ヒストリア
お伊勢参りはしたけど、出雲大社も行ってみたいなあ!
松江と同じ服装ってことは、同日ロケ?!
![]()
![]()
鳥井の場所が一番高い。「高低差ファンが建てたに違いない![]() 」と断言したタモさんだったが、
」と断言したタモさんだったが、
この後、何度も覆されてた/爆
【お題:出雲はなぜ日本有数の観光地となった?】
![]() もとは砂丘地帯だった
もとは砂丘地帯だった
![]()
![]()
![]()
「今のような賑わいになったのは、250年くらい前(江戸時代中期)なんです」
これにまずビックリ。
![]() 神在月
神在月
毎年、旧暦10月は、全国の神さまが縁結びのために集まる。
![]()
![]()
![]() 昔は全然違う造りだった説
昔は全然違う造りだった説
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ここのルールは2礼4拍手1礼。
「全国の神社は、明治に国が管理しだした時に、2礼2拍手1礼にしなさいって決めたんですけど、
昭和になって元に戻してもよいことになって、ここは戻したんです」
![]() なかなか見えない本殿
なかなか見えない本殿
![]()
![]()
![]()
![]()
本殿の正式名は「大社(おおやしろ)」。「すべて竹の釘で留めている。50~60年が限界」
天井画
![]()
「“八雲之図”ていうんですけど、なぜか7つしかない。8つ描いてしまうと完成してしまうので、
完成させないことで永遠性を求めているのではないか」(ロマンだねぇ
![]()
![]()
全国から来る神様用の19の扉があるという
「すべて木で造っているから修理する必要がある。
石で造ればモアイとかピラミッドとか、遺跡になっちゃいますから」
![]() 江戸時代までは「杵築(きづき)大社」「きづきおおやしろ」と呼ばれていた
江戸時代までは「杵築(きづき)大社」「きづきおおやしろ」と呼ばれていた
![]()
![]()
家マークかあいい
![]() 本当の中心参道は別の場所!
本当の中心参道は別の場所!
![]()
![]()
「出雲御師」と呼ばれる神職さんたちが全国に出雲大社を宣伝して歩いた
神門通りと大鳥居ができたのは大正時代!驚
![]() 玉を持っている大国様があちこちに
玉を持っている大国様があちこちに
大国様(オオクニヌシ)と読み、みんなの知っている大黒様とは別人。
![]()
![]()
![]() 「四つ角」を通って御師たちは全国に布教に行った
「四つ角」を通って御師たちは全国に布教に行った
![]()
布教に使った版木
![]()
![]()
ダンボール箱3つくらい、70以上もの版木が屋根裏から見つかった/驚
![]() タモさんが版木を刷る体験~40年以上の職人の体で/爆
タモさんが版木を刷る体験~40年以上の職人の体で/爆
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
出てきた文字は「蕎麦預」
「信者の方々がお参りして、これを持ってくると1杯無料になるという券ですね」w
![]()
![]()
イチオシのご利益を「縁結び![]() 」としたことで大人気となった
」としたことで大人気となった
![]() 中世の道にある豪邸
中世の道にある豪邸
![]()
![]()
「江戸初期くらいから徳川幕府の許可を得て、8月1~8日までの8日間催して大繁盛し、大社の修復代にあてた。
年2回あって、今のお金でいえば総額23億円。一大産業ですよ」
![]()
![]()
![]()
再現でCG
![]() 大社駅
大社駅
![]()
![]()
明治に鉄道が出来て、観光客が押し寄せた。
「今、日本で駅舎の国の重要文化財は3つあり、赤レンガの東京駅、門司港駅と、この大社駅です」
切符売り場とその中
![]()
![]()
![]()
![]()
「3円です」と言われて払おうとしたら、今のお金に換算されて「11200円です」ww
![]()
![]()
![]()
![]()
昭和30~45、6年くらいまでが最盛期だったが、その後新しい駅が出来て、平成2年に廃線
![]()
![]() 大社駅が出雲大社から遠い理由
大社駅が出雲大社から遠い理由
![]()
10年前にお客が減り、リニューアルしたが、2つのメインストリートから同じ距離に造ったため遠くなった
そしてできた今のメインストリート
![]()
![]()
![]() 絶大なスイーツ効果
絶大なスイーツ効果
「今は若い女性客がスイーツ目当てで大勢来て、以前の8倍以上の来客数となった」
「そして、町のカンフル剤的になっているのが、やはり遷宮なんです。町の人々も、それによって復活していく」
![]()
そして、例によってスイーツは食べない「ブラタモリ」w
(なんだか金儲けの話で、イメージが随分変わったな![]()
【ブログ内関連記事】
 出雲 縁結びの旅へ!@歴史秘話ヒストリア
出雲 縁結びの旅へ!@歴史秘話ヒストリアお伊勢参りはしたけど、出雲大社も行ってみたいなあ!
松江と同じ服装ってことは、同日ロケ?!


鳥井の場所が一番高い。「高低差ファンが建てたに違いない
 」と断言したタモさんだったが、
」と断言したタモさんだったが、この後、何度も覆されてた/爆
【お題:出雲はなぜ日本有数の観光地となった?】
 もとは砂丘地帯だった
もとは砂丘地帯だった


「今のような賑わいになったのは、250年くらい前(江戸時代中期)なんです」
これにまずビックリ。
 神在月
神在月毎年、旧暦10月は、全国の神さまが縁結びのために集まる。


 昔は全然違う造りだった説
昔は全然違う造りだった説





ここのルールは2礼4拍手1礼。
「全国の神社は、明治に国が管理しだした時に、2礼2拍手1礼にしなさいって決めたんですけど、
昭和になって元に戻してもよいことになって、ここは戻したんです」
 なかなか見えない本殿
なかなか見えない本殿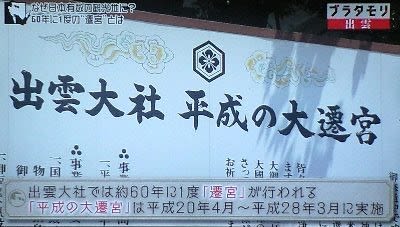



本殿の正式名は「大社(おおやしろ)」。「すべて竹の釘で留めている。50~60年が限界」
天井画

「“八雲之図”ていうんですけど、なぜか7つしかない。8つ描いてしまうと完成してしまうので、
完成させないことで永遠性を求めているのではないか」(ロマンだねぇ


全国から来る神様用の19の扉があるという
「すべて木で造っているから修理する必要がある。
石で造ればモアイとかピラミッドとか、遺跡になっちゃいますから」
 江戸時代までは「杵築(きづき)大社」「きづきおおやしろ」と呼ばれていた
江戸時代までは「杵築(きづき)大社」「きづきおおやしろ」と呼ばれていた

家マークかあいい
 本当の中心参道は別の場所!
本当の中心参道は別の場所!

「出雲御師」と呼ばれる神職さんたちが全国に出雲大社を宣伝して歩いた
神門通りと大鳥居ができたのは大正時代!驚
 玉を持っている大国様があちこちに
玉を持っている大国様があちこちに大国様(オオクニヌシ)と読み、みんなの知っている大黒様とは別人。


 「四つ角」を通って御師たちは全国に布教に行った
「四つ角」を通って御師たちは全国に布教に行った
布教に使った版木


ダンボール箱3つくらい、70以上もの版木が屋根裏から見つかった/驚
 タモさんが版木を刷る体験~40年以上の職人の体で/爆
タモさんが版木を刷る体験~40年以上の職人の体で/爆




出てきた文字は「蕎麦預」
「信者の方々がお参りして、これを持ってくると1杯無料になるという券ですね」w


イチオシのご利益を「縁結び
 」としたことで大人気となった
」としたことで大人気となった 中世の道にある豪邸
中世の道にある豪邸

「江戸初期くらいから徳川幕府の許可を得て、8月1~8日までの8日間催して大繁盛し、大社の修復代にあてた。
年2回あって、今のお金でいえば総額23億円。一大産業ですよ」
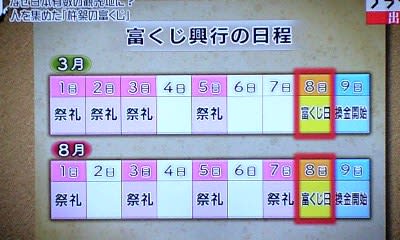


再現でCG
 大社駅
大社駅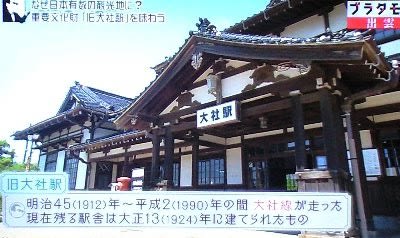

明治に鉄道が出来て、観光客が押し寄せた。
「今、日本で駅舎の国の重要文化財は3つあり、赤レンガの東京駅、門司港駅と、この大社駅です」
切符売り場とその中


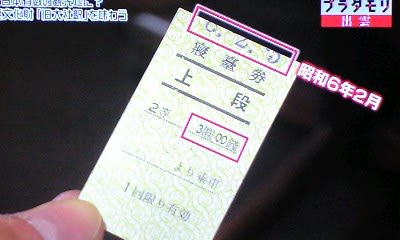

「3円です」と言われて払おうとしたら、今のお金に換算されて「11200円です」ww


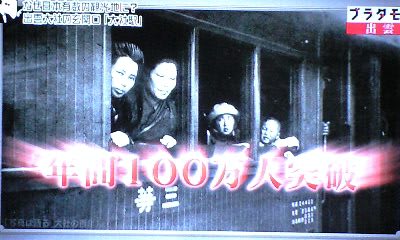

昭和30~45、6年くらいまでが最盛期だったが、その後新しい駅が出来て、平成2年に廃線

 大社駅が出雲大社から遠い理由
大社駅が出雲大社から遠い理由
10年前にお客が減り、リニューアルしたが、2つのメインストリートから同じ距離に造ったため遠くなった
そしてできた今のメインストリート


 絶大なスイーツ効果
絶大なスイーツ効果「今は若い女性客がスイーツ目当てで大勢来て、以前の8倍以上の来客数となった」
「そして、町のカンフル剤的になっているのが、やはり遷宮なんです。町の人々も、それによって復活していく」

そして、例によってスイーツは食べない「ブラタモリ」w
(なんだか金儲けの話で、イメージが随分変わったな
