■『魔法としての言葉 アメリカ・インディアンの口承詩』(思潮社)
金関寿夫/訳・著
【ブログ内関連記事】
![]() 『アークティック・オデッセイ 遙かなる極北の記憶』(新潮社)
『アークティック・オデッセイ 遙かなる極北の記憶』(新潮社)
![]() 『アメリカ・インディアンはうたう』(福音館書店)
『アメリカ・インディアンはうたう』(福音館書店)
![]() 『魔法のことば エスキモーに伝わる詩』(福音館書店)
『魔法のことば エスキモーに伝わる詩』(福音館書店)
星野道夫さんの著作で金関寿夫さんのことを知り、『魔法としての言葉』の他の詩も読んでみたいと思って借りた。
こないだ借りた『日本語を味わう名詩入門1 宮沢賢治』(あすなろ書房)とリンクして、詩=癒やし(ヒーリング)だったんだと知った。
【内容抜粋メモ】
![]() 「アメリカ・インディアン」とは
「アメリカ・インディアン」とは
アメリカ・インディアンの定義は難しい。かれらの文化があまりに多種多様だからだ。
かれらの中には、自分たちを「ネイティヴ(先住)・アメリカン」と呼んでほしいという要求が高まっている。
だが本書では、日本ではまだ通りがいいということで、従来の呼称「アメリカ・インディアン」を使っている。
そして、主にエスキモーを含む北米大陸の詩・民話に限定している。
インディアンの文化様式の多様性は、北米大陸の風土・地勢の多様性の影響を受けている。
住居![]() にしても、「長屋(ロングハウス)」、共同家屋、アパート式集合住宅、ホーガン、テント、ウィグワム、ウイキァップ、ティピーなどなど。
にしても、「長屋(ロングハウス)」、共同家屋、アパート式集合住宅、ホーガン、テント、ウィグワム、ウイキァップ、ティピーなどなど。
言葉の種類は千以上だといわれる。
食物取得方法も、狩猟、採集(漁獲![]() )、農耕(牧畜)に大別される。
)、農耕(牧畜)に大別される。
農産物は、昔からトウモロコシ、タバコ![]() が多い。
が多い。
ヨーロッパの初期植民者が、かれらからタバコを知り、広がっていった。
インディアンにとってのタバコは、嗜好品ではなく、呪術的、儀式的な意味がある。
そういう多様性にも関わらず、神話や世界観の本質的な同質性は否定できない。
彼らの大部分が、太古に、ベーリング海を渡って、アメリカ大陸に移住したアジア系の人種らしい![]()
私たち日本人にも容貌がとても似ていて、祖先を共有していたかもしれないと容易に想像できる。
北米南西部~中南米の諸部族のように、主に太平洋の島々![]() を経由して渡来した者もいると分かってきている。
を経由して渡来した者もいると分かってきている。
![]()
![]() 「アメリカ・インディアン」の詩の翻訳の難しさ
「アメリカ・インディアン」の詩の翻訳の難しさ
詩は、翻訳の場合、原詩の音楽性を日本語で再現するのは不可能だ。もとの言葉との音韻体系がまったく違うから。
言葉の響き、音のリズムは、詩の生命。意味は翻訳できても、音楽性は翻訳できない。
もう1つの問題は、文字を持たないかれらの「口承詩」を一度、英語表記したものを、さらに日本語にする二重の手続きだ。
これは残念だが仕方がない。
もっと厄介なのは、詩が本来もつ「呪術的な性格をはたしてどれだけ伝えられるか」。
理想は、かれらの「神話」を共有していなければならない。
その場のパフォーマンス(発声者の声の出し方、身ぶりなど)臨場感が大切だ。
ジェローム・ローゼンバーグは、パフォーマンスとしての朗読をやっている詩人。
私にインディアンの口承詩を教えてくれたのは、詩人のゲイリー・スナイダー。
「カリフォルニアのインディアンは、コヨーテの声は“地霊”の声だと信じている」
と彼は言っていたのが、それ以後、耳について離れなくなった。
アメリカ文学は、長い間、自分の「根」を、アメリカ大陸ではなく、ヨーロッパに求めていた。
だがいまや、彼らが住みついた大陸に根をおろして約300年。
北米大陸の文化全体が、このもっと古い「根」に同化しつつある。
ジェロームらは、詩人とは「呪術師(シャーマン)」であり、詩は「治療(ヒーリング)」のために存在する、と考えている。
・インテレクチュアル(intellectual)=知的なさま。知性を必要とするさま。
![]()
**************************「アメリカ・インディアン」の口承詩
詩人ケネス・レクスロスは、
「スミソニアン・インスティテューション、アメリカ民族学局は、アメリカ・インディアンの口承文学の宝庫だ」と指摘。
しかし、その存在に注目する者はほとんどいないことを嘆いた。
アメリカ・インディアンの口承詩は、アメリカ文学史に容認されていない。
これは、明らかに「白人中心主義的」な「史観」だ。
その背景には、殖民以来、白人がインディアンに対して行った「非行」への、清教徒の末裔らしい罪の意識が働いている。
そして「口承文学」自体への、理不尽な軽視がある。
インディアンは、文字を持ったことがなかった。
それなら「ホメロス」「平家物語」はどうなのだ?
「文化的錯誤」は、こうした偏見の集積であることが多い。
昔のインディアンは、部族中の者が物語に耳を傾け、全員が歌を作り、全員が詩人だった。
文学はもっと生活に密着したもの、実用的、機能的なものだった。
宇宙の霊と交流したり、超自然の能力を獲得するための、呪術的な媒介として歌があった。
詩作は「ヴィジョン」を見て、それを言葉にすることだった。
「かれらの歌とは、ヒトと、宇宙の中の目に見えない存在との間に交わされる伝達の手段だ」(研究家アリス・C・フレッチャー)
例えば、実りを切実に願う、雨乞い、病を治すなど。
彼らにとっては、鳥獣、山川草木、ヒトにも差別がない。同じ心を持ち、同じ権利を持っていると考える。
ゲイリー・スナイダーが若いインディアンと木こりをしていたら、彼は家に帰りたいと言い出した。
「この頃、木を切っていると、木の悲鳴が聞こえてたまらないんだ」
「岩」ですら人格化され、聖化される。
永遠に「休んでいる」岩は、畏敬に値する彼らの父、祖父、おそらく神でもあるのだ。
「天体を生命あるものとして考えるよう教えられ、すべての動物の中に人間以上の力を見出し、
山も木も石も、あらゆるものが生命、ないしいろいろな感性を具えると信じている」(研究家フランツ・ボアス)
「西欧人は、自己を、敵対する環境の中の独立した実態とみなし、滅び行く世界における比較的永続的な要因で、
かつその中で唯一の価値在る存在だと見ている。
だが、アメリカ・インディアンの詩が生まれる前の強度な美的認識は、
自己と慈愛に満ちた環境が同一物だという認識にほかならない」(レクスロス)
1920年代、インディアン文学が、日本の俳句や短歌と比較され、一時もてはやされた。
エズラ・パウンドが提唱した「イマジズム運動」の普及で、イメージを主体とする短い叙情詩が流行ったことも関係する。
インディアンの歌は「人生の価値を高め、人生のあらゆる価値が危機に瀕している今日、それを無視するのは有益ではない」(レクスロス)
1960年代の「カウンター・カルチャー」運動で、彼らが否認した「西洋合理主義世界観」の逆として、
「プリミティヴ」な世界観が急に人気を得る。
インディアン側からの「レッド・パワー」の高まりもあった。
ミネソタの詩人ロバート・ブライなど、「ヴィジョナリー」な伝統の回復を目指す詩人も多い。
いまや、英語で書く同時代のインディアン作家も出てきて、すでに文学史の中に地位を得ている。
スコット・ママディー、レスリー・マーモン・シルコーなど
![]()
**************************魔法としての詩
ある日、「なぜ意味のない音だけの歌を歌うのか」と白人神父がナバホ族の男に聞いた。
男は「むしろコトバには意味がない。けれどもこの歌にはちゃんと意味がある。
“さ、もっていきな。欲しければ君にあげるよ”と言っているんだ」と答えた。
「魔法の詩人が定めた目的に向かって物事を動かす。そうした特殊な言語は、
それを使う者と、彼が影響を与えようとしている生物や事物との合一を成就する」(ジェローム)
魔法というコトバを避けたければ「超言語」と呼ぶこともできる。
それは精神の最も奥深いところで交信を可能にする言語なのだ。
ヒトの口から「呪文」として出る音声、「呼吸」は宇宙の「大霊」を伝達しうるという信念がある。
「呪術師が、呪文を細心の注意をこめて、繰り返し発声している様子を見ると、
魔法は“呼吸”の中にあり、“呼吸”こそが魔法だという信仰がいかに重要かが分かる」(人類学者B.マリノフスキー)
言霊を失ったところから「文学」が始まった。その時、いわば「原罪」を得たのだ。
「文学は“naming(事物の名前を呼ぶ)”ことに始まった。
文明が進むにつれ、霊のあったコトバは、単なる記号になり、本来の瑞々しい生命を失った」(米女流作家ガートルード・スタイン)
コトバは彼らの「誓い」「良心」と等しいのである。
「天地創世の前にまずコトバがあり、コトバが神をつくった」(ウイトト・インディアンの創世神話)
「男はいつも獲物を探してあちこち無駄に歩き回る。
けれども家にいてランプのそばにじっと座っている女たちは、ほんとに強いもんだよ。
あの連中ときたら、コトバで獲物を浜に呼び寄せることを知っているんだものな」(エスキモーの男たち)
![]()
![]() シャーマン
シャーマン
「シャーマン」というコトバは、シベリア、中央アジアあたりに起源をもつらしい。
「シャーマニズム」を広義に解釈すると「エクスタシーの専門家」、したがってシャーマンは「聖なる技術者」ということになる。
シャーマンこそ、「プロト・ポエット(最も原初的な詩人)」なのだと。
「新しい詩人になるためには“見者”にならなければならない」(天才詩人アルチュール・ランボー
平原地方のインディアンにとって、超自然のヴィジョンを見ることは、一生で一番大切な行事だ。
そのために苦行をし、夢を通じて、超自然の存在が心に入り込み、それが「守り神」となる。
守り神は、魔法の歌や祈り、儀式の作法、人生の指針を与え、災いから守る。
そのお守りのことを白人は「薬袋(メディシン・バントル)」と呼ぶ。
「秘密の名前と、守護してくれる動物の霊と、秘密の歌を持ち、それが彼の力となる」(G.スナイダー)
ナホバ族の世界観によると、この世界に住む生物は、単なる「地表に住むもの」と「聖なる存在」の2種類に分類される。
後者は、この世に乱れが生じた時、なおす力をもつ。
つまり、すべての災厄(病も含め)は、あるべき「調和の乱れ」で、それを治癒し、回復するのが「聖なる存在」であり、
シャーマン、「メディシンマン」である。
彼らは病気治癒に「砂絵(サンドペインティング)」を描き、これは歌と同様、一回性だから、
用が済むと跡形もなく消されてしまう。
私たち近代人は、意識の深いところで、かれらの神話を共有できなくなっている。
「神話とは、基本的で、永久に消えることのない、生命の連帯についての深い信仰だ」(カッシーラ)
![]()
**************************詩
例の「魔法のことば」からはじまる。
ルーシュー族の「暦」で、6月が「動物の毛が抜け変る月」ってステキ![]()
「たれかがどこかで」(テトン・スー族)
たれかが
どこかで
話している
聖なる石の国の民が
話している
きみは聞くだろう
たれかが
どこかで
話しているのを
「夜の歌より」(ナバホ族)
夜よ
あなたはわたしの美しい代理人となる
あなたはわたしの美しい歌となる
あなたはわたしの美しい霊薬となる
あなたはわたしの美しい神聖な薬となる
「春のフィヨルド」(エスキモー族)
おれはカヤックで沖に出ていた
おれはカヤックで海に出ていた
アマシヴィク・フィヨルドの海で
おれはとても静かに漕いでいた
海には氷が張っていた
それからウミツバメも一羽いて
頭をあっちやこっちに動かせていた
おれが漕いでいるのには気がつかなかった
急にやつの尻尾しか見えなくなった
つぎにはなんにも見えなくなった
やつが潜ったのは別におれのせいじゃなかった
海面にでっかい頭が急に浮かんだからだ
でっかくて毛深いアザラシだ
どでかい頭に どでかい眼をして
ひげは陽光に輝き しずくをザアザア垂らしていた
しかもそいつは おれのほうへゆっくりやってくるじゃないか
なぜおれは やつに銛を一発ぶちこまなかったんだろう
やつのことをかわいそうに思ったからか
それともそれは その日
その春の日のせいだったんだろか
アザラシが おれとおなじように 陽光の下で遊んでいた
あの春の日―――――
![]()
「コヨーテじいさんの天地創造」(クロー族)
周りが水ばかりだった頃、コヨーテじいさんとアヒル2羽しかいなくて寂しいから、いろいろなものを創り始めるw
アヒルに頼んで海底から土を持ってきてもらい陸をつくる。そこに果物や草木をつくる。
「おれたちには友だちがまったくねえ。これじゃ退屈でどうしようもねえよ」
そこでひと塊の土で男をつくる(やっぱ男が先なの?![]()
アヒルも雄だけで増えようがないから、女のヒトと、雌のアヒルをつくる。
「アヒルだけってのは、少し淋しいんじゃない?」と言われて、なるほどと、鹿、エルク、羊、熊![]() をつくる。
をつくる。
ライチョウもつくって「美しい鳥はたくさんいる。おれはお前をわざと美しくは作らなかったが、特別の力を与えた。
太陽が昇るたびに、お前は踊りを踊るんだ」こうして生物すべてが楽しめるものが持てた。
でも熊![]() は全然、満足しない。「そいつに合わせて踊る音みたいなものはできねえもんかね?」
は全然、満足しない。「そいつに合わせて踊る音みたいなものはできねえもんかね?」
なるほどと、ハリモミ雷鳥に歌をやり、ドラムを打ち鳴らし、みんなが踊った。
まだ熊![]() は満足しないばかりか「俺はでっかくて偉いんだ。だから俺だけが踊る力を持つべきなんだ」と文句を言った。
は満足しないばかりか「俺はでっかくて偉いんだ。だから俺だけが踊る力を持つべきなんだ」と文句を言った。
とうとう怒ったコヨーテじいさん。
「無礼者! こいつはでっかい爪で、小さな動物たちを脅そうとしてるんだ。
お前は俺たちと一緒に住んじゃいけねえ。自分だけで洞穴に入って、腐ったものを食って生きるんだ。
そして冬の間は、ずっと眠ってるんだ。お前の面なんぞ、見たくもねえからな![]() 」
」
もう1匹のコヨーテ、シラペは「あんたが作った人間の暮らしは貧しすぎる。
あいつらには道具が必要だ。住むためのティピー(テント)、煮炊きしたり、身体を温めたりする火もね![]() 」
」
「お前の言うとおりだ」コヨーテは稲妻![]() から火をとって、人々に与え、みんな大喜びした
から火をとって、人々に与え、みんな大喜びした![]()
「ついでに人間には、弓矢や槍を与えてやれば、もっとうまく狩りができると思うんだけれど。
だけどね、兄貴、武器をやるのは人間だけで、動物には禁物だよ。
動物は動きが速い。大きな爪や歯、恐ろしい角をすでに持っている。ところが人間は動きがのろい。
その上、歯や爪も決して強くない。だから、もし動物がこの上、弓矢を持ったら、人間はとても生き残れねえよ」
「なるほど、弟よ、お前はすべてによく頭が回るやつだ。これでいいかい?」
「いや、いや、とんでもねえ。まだあるね。人間の言葉は今ひとつしかない。
人間は、自分と同じ言葉を喋る相手とは戦はできねえ。だから敵が必要だ。戦が必要だ」
「戦だって? そんなのなんの役に立つんだい?」
「戦はいいもんだよ。あんたは顔を朱色の絵の具でくまどる。出陣し、立派な手柄をたてる。
村の美しい若い娘を見つめると、彼女らも熱っぽく見つめかえすって寸法だ。
敵の馬![]() や、妻や、娘をかすめ取る。金持ちになる。みんなはあんたを褒め称えて、あんたはもうピカンピカンだ
や、妻や、娘をかすめ取る。金持ちになる。みんなはあんたを褒め称えて、あんたはもうピカンピカンだ![]() 」
」
「シラペ。お前の言うことはまことに的を射ている」
そこでコヨーテじいさんは、ヒトをいくつもの部族に分けて、違った言葉を与えた。
すると実際、いたるところで戦争![]()
![]()
![]() が起こり、戦功を讃える歌声が轟いた。
が起こり、戦功を讃える歌声が轟いた。
「他人の女房を盗むって、あれは実にいいもんだ。俺たちの部族でも、妻の寝取り合いの習慣が続いている。
ところで弟よ、もしお前の女房が、もう一度お前のところへ戻ってきたら、彼女を家に入れてやるかね?」
「とんでもねえ! 俺にだって誇り、自尊心ってものがある!」
「シラペよ、お前はほんとに馬鹿もんだ。ものの道理ってものが分かっちゃおらん。
俺の女房は、3度も他の野郎にさらわれた。けれど帰ってくるたび、俺は家に入れてやった。
だから今では、なにかを命令すると、いつもあいつは、昔さらわれたことを思い出す」
そういうわけで、昔クロー族の間では、家族間に女房の盗み合いが盛んに行われ、
いったん別れた妻が帰ってきた時、平気で受け入れるのも、もとをただせば、
あのコヨーテじいさんまでさかのぼる、というわけなのです。
(どうも、後半が気に食わないなぁ・・・性の自由っていうなら分かる気もするけど![]()
【訳注】
コヨーテは、アメリカ狼のことだが、アメリカ・インディアンの民話や詩には、最も魅力的な文化ヒーローとして頻繁に登場する。
神通力を持っていて、ヒトや他の動物をよくペテンにかけるが、自分も失敗して酷い目に遭うことが多いw
他のインディアンの「トリックスター」、ウサギ![]() 、カラスなどのように、
、カラスなどのように、
ヒトや自然が織りなすリアリティの上に行使された喜劇的な想像力の産物は、ヒトすべてに共通する意識で、
コヨーテが象徴する「破壊性」や「論理的非一貫性」は、西欧近代社会が価値を置いてきた「秩序」とは、本質的に相容れないものではなく、
むしろ社会を活性化するのに役立つと、文化人類学的解釈によって、近年ますます人気が増している。
(どこかで、そんな風なことを読んだな。協調性のないような人がいると、案外突飛なアイデアを出して、組織を活発化させる、みたいな
【訳注2】
「笑いはそれ自体、宗教的言語の古い形態だ」(ジェローム・ローゼンバーグ)
シャーマンは薬がヤカンの中で煮えている間、儀式用の「吹管(ブローパイプ)」を吹かしながら詩を唱える。
「トータル・トランスレーション」(インディアンの口承詩の持つ、聴覚的・視覚的要素をトータルに捉えたローゼンバーグの試み)
![]()
**************************白人侵入後
「アメリカへいちばん早く来た私たちは、いちばん遅く、やっと1921年にアメリカ人になった」(レスリー・マーモン・シルコー)
「おれの若者たちは働いてはいけない」
おれの若者たちは働いてはいけない
働く男は夢を見ることができないからだ。そして最高の知恵は夢の中で授かる。
君たち白人は、俺に土地を耕せという。
君たちは俺にナイフをとって母なる大地の乳房を切り刻めというのか。
そんなことをすれば俺が死んだ時、母は俺をその胸に抱きとり休ませてはくれないだろう。
(中略)
君たち白人の法律は悪い法律だ。俺の民はそんなものに従うことはできない。
俺は俺の民がここに、俺と一緒にいつまでもいてほしいのだ。
すべての死んだ仲間は、再び生を得るだろう。
俺たちは俺たちの父祖の家に留まり、俺たちの母のからだの中にいる彼らに再会する日を待たねばならない。
【訳注】
北米大陸に渡来した白人は、白人式に働くことを拒むインディアンを“救いがたい怠け者”と考えていた。
天才的科学者で進歩主義の権化のようだったベンジャミン・フランクリンの手紙によると、
アメリカ植民地にあるイギリス政府がインディアン連邦に対して、彼らの有望な子弟を預かり、
英国費で大学に入れ、西欧風に教育してやろうと申し出をした際、連邦側の反応をこう書いている。
「われらの子弟の何人かがすでに以前その大学で教育を受けたが、まったく無能者になっていた。
鹿を殺したり、ビーバーを捕えたりする方法を会得するまでに長年を要するていたらく。
しかしながら、英国の申し出は、連邦に対する好意と親善とみなし、感謝をこめた返礼をするにやぶさかではない。
もし英国側の紳士らの子弟をオノンダゴまで送ってくれれば、私たちは喜んで彼らの教育を引き受け、
真に最善の方法で彼らを一人残らず立派な男に仕立て上げてしんぜよう」(痛快だね![]()
フランクリンはこう言った。
「インディアンたちにラム酒![]() さえ与えれば、北米大陸からすべての野蛮人を掃蕩することができるだろう」
さえ与えれば、北米大陸からすべての野蛮人を掃蕩することができるだろう」
その基本的態度は、極めて政治的、外交的で、「野蛮人を見下す文明人」だったことは間違いない。
白人たちが16C、北米大陸に殖民をはじめて以来、インディアンは様々な形で白人文明と接触し、
最後には「ウンデッド・ニーの惨劇」に終わった歴史がある。
とくに中西部、西部開拓が、もっとも強引に進んでいった。19Cに起こった白人文明の西進運動は、
インディアンの「聖なる土地」に決定的な圧力をかけた。
インディアン![]() 白人だけでなく、インディアンの部族同士の紛争も激化した
白人だけでなく、インディアンの部族同士の紛争も激化した![]()
![]()
![]()
部族同士を相克させることで絶滅をはかる一方、間接的な破壊的手段も持っていた。
伝染病(はしか、天然痘、性病)、鉄砲、ラム、ウイスキー、キリスト教(彼らの伝統的な神話や世界観を破壊した)など。
「冬の啓示」(ダコタ・インディアン)(抜粋)
白人は神の四つの黒い旗があることを知っている。それは大地の四つの要素なのだ。
わたしこそ、鷲の女だ。わたしは女だから、この神の家に血を流すことには同意できない。
長い年月の後、お前は白人と一緒に暮らすようになるからだ。
インディアン娘ポカホンタスとのロマンスで有名なキャプテン・ジョン・スミスのスピーチ。
「愛をもってすれば得ることができるかもしれないものを、なぜ君たち(イギリス人植民者)は力によって強奪しようとするのか。
君たちに食物を分けてあげいるオレたちを、なぜ君たちは滅ぼそうとするのか。戦によって何が得られるというのか。
オレたちには武器がない。それに、もし君たちが友好的な態度で来るなら、喜んで欲しいものを分けてあげると言っているのだ。
美味い肉を食べて安眠し、自分の女や子どもと平和に暮らし、イギリス人たちとも楽しく笑って友だち付き合いをし、
イギリス人の銅器と、オレたちの斧を交換し合って生きるほうが、彼らから絶えず逃げながら暮らす生活よりもはるかに好ましい。
オレはそのくらいなことが分からないほどの大馬鹿だろうか。
まず銃や剣を捨てなさい。それこそが、オレたちの妬みの元なのだから。
さもなくば、君たちがおれたちを殺すのと同じ方法で、君たちも亡びるだろう」
とくに初期開拓者は、清教徒的感覚から、インディアンを、キリスト教に敵対する「悪魔の化身」と見ていた。
白人の彼らに対する恐怖と敵意の激しさは、言葉に尽くせないものだった。
その心理の半面は、有色人種に対する積年の「白人優越主義」が働いていた。
シャイアン族の「白かもしか(ホワイト・アンテローブ)」と言われた隊長も、1864年の「サンド・クリークの大虐殺」で戦死した。
彼は、弾丸を受けて地に倒れる直前、腕を組んで大地に立ったまま、この歌を詠んだという。
「白かもしかの歌える死の歌」
すべてのものは亡びる
すべてのものは亡びる
すべてのものは亡びる
大地と山々のほかは
この虐殺後、白人兵は彼の陰嚢を切り取りタバコ入れを作ったという。
(ヒトはそれほど冷酷になれるものか。狩った動物の剥製を飾って楽しむようなものか
![]() 「ゴースト・ダンス」
「ゴースト・ダンス」
インディアンたちは戦においても屈服しなかったが、文学においても、白人を神話と伝説の中にやがて組み込んでしまう。
最もユニークなものは「ゴースト・ダンス」の歌だろう。
「ゴースト・ダンス」とは、19C末に起こったインディアンの一種の宗教的民族主義運動だった。
だが皮肉にも、まったく異質のキリスト教の影響を受けた、救世主再臨を願う「リヴァイヴァリズム運動」でもあった。
この中心的な信仰は“いずれこの現世は亡びるだろう。だがいつか救世の神が現れて、救いが到来する”。
この最初の預言者は、デラウエア族のシャーマンだった。
もしインディアンが、白人社会の物質主義を排して、本来の生き方に専念したら、いずれ白人らはこの大陸を去るだろうと予言した。
最も有名なリーダーの一人「ハンサム・レーク」は、彼らの渇仰を集めた。
しかし、彼らが信じた真の「救世主」は、パイユート族のウォヴォカだった。
「すべてのインディアンがゴースト・シャツを着て、そのダンスを踊れば、野牛が地から立ち上がり、
夢の中で白人を踏み殺し、すべての鳥や獣が帰ってきて、アメリカの土地は、すべてインディアンの手に戻るはずだ」
すべてのインディアンが、白人の絶滅を信じたのである。
「ゴースト・ダンス」は、一種の恍惚、夢に入った踊り手が、その中で受け取る歌を歌う儀式だった。
これは、本来は平和的なものだった。一部を除けば、白人に直接戦闘を挑む者はいなかった。
精神的なレジスタンス運動だったが、これに苛立った一部のアメリカ政府軍は、明らかに防備の劣ったインディアン部落を急襲し、
婦女子を含む200人のスー族を殺した。1890年12月29日「ウンデッド・ニー」の事件だった。
![]() 「ゴースト・ダンス」の詩
「ゴースト・ダンス」の詩
「わたしは彼らに果物をやった」
子どもたちよ はじめわたしは白人たちが好きだった
わたしは彼らに果物をやった
わたしは彼らに果物をやった
父よ きいてくれ
わたしの咽喉はカラカラだ
わたしの咽喉はカラカラだ
ここにはもうなんにもない
ひとかけらの食べ物も
【訳注】
これらは文学的には、他の詩と較べて少し質が落ちるかもしれないが、
「おれたちはよみがえるぞ(ヒ・ニスワ・ビタニキ)」という彼らの声は、
インディアンはもちろん、白人の耳にも残響が続いている。
ベトナム戦争がたけなわな頃に、ゲイリー・スナイダーはこう書いた。
「アメリカ・インディアンとは、悩めるアメリカ人の心の奥に潜んでいる復讐に燃える幽霊なのだ。
だからこそ我々は、あれほどの残忍と情熱をもって、しかし心の中ではひどく混乱しながら、
“ベトコン”という髪の黒い若い農夫や兵士を殺している」
「白人はおれに貯えろと言う」(フレッド・レッド・クラウド)
白人はおれに言う
貯えろと
そこでおれは貯える
紐や 煉瓦や 木や馬や 革などを
ところがだれひとり
おれが貯えたものなどほしがらない
そこでおれは砂漠へ行って 直径四尺もある
おれが貯えた紐の玉をころがしてみる
そこへ やってきたのが白人二人
おれが貯えた煉瓦や 木や 馬や
革や 紐を そいつらは見る
そして おれに訊ねていわくには
おまえ そんなもの いったいどこで盗んだのだい?
おれの弁解なぞ 聞く耳もたぬと
やつらは 紐をおれから取りあげる
そしてそいつを
ロープに編んで
こんどはそれを
おれの首に巻きつける
そしておれがせっかく貯えた木の枝から
おれを吊るし首にしたんだとさ
「盗人」
おれたちは兵士だったから
戦争の意味は知っていた
勝ったほうが全部取るのだ
おれたちは外交官だったから
嘘の意味は知っていた
といってたいしておえら方じゃなかったけれど
おれたちは民主党だったから
政治の意味は知っていた
人間は人間だ
きみたちはおれたちの土地を盗(と)った
おれたちはそういうきみたちを 理解しようとした
だがきみたちはそこに住みついただけで その土地を愛さなかった
わが友よ
(たしかにきみたちなりの友情でもって、しばしばきみたちはおれたちのよき友であった)
だがそれにしてもわが友よ
いったいどういうわけできみたちは
おれたちの子どもの口元から
あのほほえみを盗んだのかね?
最後に現役インディアン作家レスリー・シルコーの美しい詩の終わりの数行をあげておく。
インディアン詩の伝統精神は、今もこうして脈々と続いているのだ。
「太平洋への祈り」
3万年前
巨大な海がめにまたがって![]()
インディアンは 海原こえてやってきた
その日 波は高かった
大きな海がめたちは 灰色に煙る日暮れの海から
ゆっくりと這い上がってきた
祖父がめは 砂のなかで 四度ころがって
太陽のなかに泳ぎ入り
消えていった
そういうわけで
その昔から
老人たちも言うように、
海からの贈り物 雨雲は
西の方から漂ってくる
風に舞うみどりの木の葉
中国から ずっとやってきた
雨を呑みこんで
わたしの足の 濡れた土
**************************あとがき
拙著『アメリカ・インディアンの詩』(中公新書 1977年刊)が絶版になった。
それを思潮社が出してあげてもいいと言ってくれた。
子守唄など詩を増やし、トリックスターの話を2、3入れた。
【註】
ホピ族のコトバには「性別(ジェンダー)」が存在しない。
ホピ語の名詞は、無生物でも明らかに「生きたもの」として取り扱われている。
金関寿夫/訳・著
【ブログ内関連記事】
 『アークティック・オデッセイ 遙かなる極北の記憶』(新潮社)
『アークティック・オデッセイ 遙かなる極北の記憶』(新潮社) 『アメリカ・インディアンはうたう』(福音館書店)
『アメリカ・インディアンはうたう』(福音館書店) 『魔法のことば エスキモーに伝わる詩』(福音館書店)
『魔法のことば エスキモーに伝わる詩』(福音館書店)星野道夫さんの著作で金関寿夫さんのことを知り、『魔法としての言葉』の他の詩も読んでみたいと思って借りた。
こないだ借りた『日本語を味わう名詩入門1 宮沢賢治』(あすなろ書房)とリンクして、詩=癒やし(ヒーリング)だったんだと知った。
【内容抜粋メモ】
 「アメリカ・インディアン」とは
「アメリカ・インディアン」とはアメリカ・インディアンの定義は難しい。かれらの文化があまりに多種多様だからだ。
かれらの中には、自分たちを「ネイティヴ(先住)・アメリカン」と呼んでほしいという要求が高まっている。
だが本書では、日本ではまだ通りがいいということで、従来の呼称「アメリカ・インディアン」を使っている。
そして、主にエスキモーを含む北米大陸の詩・民話に限定している。
インディアンの文化様式の多様性は、北米大陸の風土・地勢の多様性の影響を受けている。
住居
 にしても、「長屋(ロングハウス)」、共同家屋、アパート式集合住宅、ホーガン、テント、ウィグワム、ウイキァップ、ティピーなどなど。
にしても、「長屋(ロングハウス)」、共同家屋、アパート式集合住宅、ホーガン、テント、ウィグワム、ウイキァップ、ティピーなどなど。言葉の種類は千以上だといわれる。
食物取得方法も、狩猟、採集(漁獲
 )、農耕(牧畜)に大別される。
)、農耕(牧畜)に大別される。農産物は、昔からトウモロコシ、タバコ
 が多い。
が多い。ヨーロッパの初期植民者が、かれらからタバコを知り、広がっていった。
インディアンにとってのタバコは、嗜好品ではなく、呪術的、儀式的な意味がある。
そういう多様性にも関わらず、神話や世界観の本質的な同質性は否定できない。
彼らの大部分が、太古に、ベーリング海を渡って、アメリカ大陸に移住したアジア系の人種らしい

私たち日本人にも容貌がとても似ていて、祖先を共有していたかもしれないと容易に想像できる。
北米南西部~中南米の諸部族のように、主に太平洋の島々
 を経由して渡来した者もいると分かってきている。
を経由して渡来した者もいると分かってきている。
 「アメリカ・インディアン」の詩の翻訳の難しさ
「アメリカ・インディアン」の詩の翻訳の難しさ詩は、翻訳の場合、原詩の音楽性を日本語で再現するのは不可能だ。もとの言葉との音韻体系がまったく違うから。
言葉の響き、音のリズムは、詩の生命。意味は翻訳できても、音楽性は翻訳できない。
もう1つの問題は、文字を持たないかれらの「口承詩」を一度、英語表記したものを、さらに日本語にする二重の手続きだ。
これは残念だが仕方がない。
もっと厄介なのは、詩が本来もつ「呪術的な性格をはたしてどれだけ伝えられるか」。
理想は、かれらの「神話」を共有していなければならない。
その場のパフォーマンス(発声者の声の出し方、身ぶりなど)臨場感が大切だ。
ジェローム・ローゼンバーグは、パフォーマンスとしての朗読をやっている詩人。
私にインディアンの口承詩を教えてくれたのは、詩人のゲイリー・スナイダー。
「カリフォルニアのインディアンは、コヨーテの声は“地霊”の声だと信じている」
と彼は言っていたのが、それ以後、耳について離れなくなった。
アメリカ文学は、長い間、自分の「根」を、アメリカ大陸ではなく、ヨーロッパに求めていた。
だがいまや、彼らが住みついた大陸に根をおろして約300年。
北米大陸の文化全体が、このもっと古い「根」に同化しつつある。
ジェロームらは、詩人とは「呪術師(シャーマン)」であり、詩は「治療(ヒーリング)」のために存在する、と考えている。
・インテレクチュアル(intellectual)=知的なさま。知性を必要とするさま。

**************************「アメリカ・インディアン」の口承詩
詩人ケネス・レクスロスは、
「スミソニアン・インスティテューション、アメリカ民族学局は、アメリカ・インディアンの口承文学の宝庫だ」と指摘。
しかし、その存在に注目する者はほとんどいないことを嘆いた。
アメリカ・インディアンの口承詩は、アメリカ文学史に容認されていない。
これは、明らかに「白人中心主義的」な「史観」だ。
その背景には、殖民以来、白人がインディアンに対して行った「非行」への、清教徒の末裔らしい罪の意識が働いている。
そして「口承文学」自体への、理不尽な軽視がある。
インディアンは、文字を持ったことがなかった。
それなら「ホメロス」「平家物語」はどうなのだ?
「文化的錯誤」は、こうした偏見の集積であることが多い。
昔のインディアンは、部族中の者が物語に耳を傾け、全員が歌を作り、全員が詩人だった。
文学はもっと生活に密着したもの、実用的、機能的なものだった。
宇宙の霊と交流したり、超自然の能力を獲得するための、呪術的な媒介として歌があった。
詩作は「ヴィジョン」を見て、それを言葉にすることだった。
「かれらの歌とは、ヒトと、宇宙の中の目に見えない存在との間に交わされる伝達の手段だ」(研究家アリス・C・フレッチャー)
例えば、実りを切実に願う、雨乞い、病を治すなど。
彼らにとっては、鳥獣、山川草木、ヒトにも差別がない。同じ心を持ち、同じ権利を持っていると考える。
ゲイリー・スナイダーが若いインディアンと木こりをしていたら、彼は家に帰りたいと言い出した。
「この頃、木を切っていると、木の悲鳴が聞こえてたまらないんだ」
「岩」ですら人格化され、聖化される。
永遠に「休んでいる」岩は、畏敬に値する彼らの父、祖父、おそらく神でもあるのだ。
「天体を生命あるものとして考えるよう教えられ、すべての動物の中に人間以上の力を見出し、
山も木も石も、あらゆるものが生命、ないしいろいろな感性を具えると信じている」(研究家フランツ・ボアス)
「西欧人は、自己を、敵対する環境の中の独立した実態とみなし、滅び行く世界における比較的永続的な要因で、
かつその中で唯一の価値在る存在だと見ている。
だが、アメリカ・インディアンの詩が生まれる前の強度な美的認識は、
自己と慈愛に満ちた環境が同一物だという認識にほかならない」(レクスロス)
1920年代、インディアン文学が、日本の俳句や短歌と比較され、一時もてはやされた。
エズラ・パウンドが提唱した「イマジズム運動」の普及で、イメージを主体とする短い叙情詩が流行ったことも関係する。
インディアンの歌は「人生の価値を高め、人生のあらゆる価値が危機に瀕している今日、それを無視するのは有益ではない」(レクスロス)
1960年代の「カウンター・カルチャー」運動で、彼らが否認した「西洋合理主義世界観」の逆として、
「プリミティヴ」な世界観が急に人気を得る。
インディアン側からの「レッド・パワー」の高まりもあった。
ミネソタの詩人ロバート・ブライなど、「ヴィジョナリー」な伝統の回復を目指す詩人も多い。
いまや、英語で書く同時代のインディアン作家も出てきて、すでに文学史の中に地位を得ている。
スコット・ママディー、レスリー・マーモン・シルコーなど

**************************魔法としての詩
ある日、「なぜ意味のない音だけの歌を歌うのか」と白人神父がナバホ族の男に聞いた。
男は「むしろコトバには意味がない。けれどもこの歌にはちゃんと意味がある。
“さ、もっていきな。欲しければ君にあげるよ”と言っているんだ」と答えた。
「魔法の詩人が定めた目的に向かって物事を動かす。そうした特殊な言語は、
それを使う者と、彼が影響を与えようとしている生物や事物との合一を成就する」(ジェローム)
魔法というコトバを避けたければ「超言語」と呼ぶこともできる。
それは精神の最も奥深いところで交信を可能にする言語なのだ。
ヒトの口から「呪文」として出る音声、「呼吸」は宇宙の「大霊」を伝達しうるという信念がある。
「呪術師が、呪文を細心の注意をこめて、繰り返し発声している様子を見ると、
魔法は“呼吸”の中にあり、“呼吸”こそが魔法だという信仰がいかに重要かが分かる」(人類学者B.マリノフスキー)
言霊を失ったところから「文学」が始まった。その時、いわば「原罪」を得たのだ。
「文学は“naming(事物の名前を呼ぶ)”ことに始まった。
文明が進むにつれ、霊のあったコトバは、単なる記号になり、本来の瑞々しい生命を失った」(米女流作家ガートルード・スタイン)
コトバは彼らの「誓い」「良心」と等しいのである。
「天地創世の前にまずコトバがあり、コトバが神をつくった」(ウイトト・インディアンの創世神話)
「男はいつも獲物を探してあちこち無駄に歩き回る。
けれども家にいてランプのそばにじっと座っている女たちは、ほんとに強いもんだよ。
あの連中ときたら、コトバで獲物を浜に呼び寄せることを知っているんだものな」(エスキモーの男たち)

 シャーマン
シャーマン「シャーマン」というコトバは、シベリア、中央アジアあたりに起源をもつらしい。
「シャーマニズム」を広義に解釈すると「エクスタシーの専門家」、したがってシャーマンは「聖なる技術者」ということになる。
シャーマンこそ、「プロト・ポエット(最も原初的な詩人)」なのだと。
「新しい詩人になるためには“見者”にならなければならない」(天才詩人アルチュール・ランボー
平原地方のインディアンにとって、超自然のヴィジョンを見ることは、一生で一番大切な行事だ。
そのために苦行をし、夢を通じて、超自然の存在が心に入り込み、それが「守り神」となる。
守り神は、魔法の歌や祈り、儀式の作法、人生の指針を与え、災いから守る。
そのお守りのことを白人は「薬袋(メディシン・バントル)」と呼ぶ。
「秘密の名前と、守護してくれる動物の霊と、秘密の歌を持ち、それが彼の力となる」(G.スナイダー)
ナホバ族の世界観によると、この世界に住む生物は、単なる「地表に住むもの」と「聖なる存在」の2種類に分類される。
後者は、この世に乱れが生じた時、なおす力をもつ。
つまり、すべての災厄(病も含め)は、あるべき「調和の乱れ」で、それを治癒し、回復するのが「聖なる存在」であり、
シャーマン、「メディシンマン」である。
彼らは病気治癒に「砂絵(サンドペインティング)」を描き、これは歌と同様、一回性だから、
用が済むと跡形もなく消されてしまう。
私たち近代人は、意識の深いところで、かれらの神話を共有できなくなっている。
「神話とは、基本的で、永久に消えることのない、生命の連帯についての深い信仰だ」(カッシーラ)

**************************詩
例の「魔法のことば」からはじまる。
ルーシュー族の「暦」で、6月が「動物の毛が抜け変る月」ってステキ

「たれかがどこかで」(テトン・スー族)
たれかが
どこかで
話している
聖なる石の国の民が
話している
きみは聞くだろう
たれかが
どこかで
話しているのを
「夜の歌より」(ナバホ族)
夜よ
あなたはわたしの美しい代理人となる
あなたはわたしの美しい歌となる
あなたはわたしの美しい霊薬となる
あなたはわたしの美しい神聖な薬となる
「春のフィヨルド」(エスキモー族)
おれはカヤックで沖に出ていた
おれはカヤックで海に出ていた
アマシヴィク・フィヨルドの海で
おれはとても静かに漕いでいた
海には氷が張っていた
それからウミツバメも一羽いて
頭をあっちやこっちに動かせていた
おれが漕いでいるのには気がつかなかった
急にやつの尻尾しか見えなくなった
つぎにはなんにも見えなくなった
やつが潜ったのは別におれのせいじゃなかった
海面にでっかい頭が急に浮かんだからだ
でっかくて毛深いアザラシだ
どでかい頭に どでかい眼をして
ひげは陽光に輝き しずくをザアザア垂らしていた
しかもそいつは おれのほうへゆっくりやってくるじゃないか
なぜおれは やつに銛を一発ぶちこまなかったんだろう
やつのことをかわいそうに思ったからか
それともそれは その日
その春の日のせいだったんだろか
アザラシが おれとおなじように 陽光の下で遊んでいた
あの春の日―――――

「コヨーテじいさんの天地創造」(クロー族)
周りが水ばかりだった頃、コヨーテじいさんとアヒル2羽しかいなくて寂しいから、いろいろなものを創り始めるw
アヒルに頼んで海底から土を持ってきてもらい陸をつくる。そこに果物や草木をつくる。
「おれたちには友だちがまったくねえ。これじゃ退屈でどうしようもねえよ」
そこでひと塊の土で男をつくる(やっぱ男が先なの?

アヒルも雄だけで増えようがないから、女のヒトと、雌のアヒルをつくる。
「アヒルだけってのは、少し淋しいんじゃない?」と言われて、なるほどと、鹿、エルク、羊、熊
 をつくる。
をつくる。ライチョウもつくって「美しい鳥はたくさんいる。おれはお前をわざと美しくは作らなかったが、特別の力を与えた。
太陽が昇るたびに、お前は踊りを踊るんだ」こうして生物すべてが楽しめるものが持てた。
でも熊
 は全然、満足しない。「そいつに合わせて踊る音みたいなものはできねえもんかね?」
は全然、満足しない。「そいつに合わせて踊る音みたいなものはできねえもんかね?」なるほどと、ハリモミ雷鳥に歌をやり、ドラムを打ち鳴らし、みんなが踊った。
まだ熊
 は満足しないばかりか「俺はでっかくて偉いんだ。だから俺だけが踊る力を持つべきなんだ」と文句を言った。
は満足しないばかりか「俺はでっかくて偉いんだ。だから俺だけが踊る力を持つべきなんだ」と文句を言った。とうとう怒ったコヨーテじいさん。
「無礼者! こいつはでっかい爪で、小さな動物たちを脅そうとしてるんだ。
お前は俺たちと一緒に住んじゃいけねえ。自分だけで洞穴に入って、腐ったものを食って生きるんだ。
そして冬の間は、ずっと眠ってるんだ。お前の面なんぞ、見たくもねえからな
 」
」もう1匹のコヨーテ、シラペは「あんたが作った人間の暮らしは貧しすぎる。
あいつらには道具が必要だ。住むためのティピー(テント)、煮炊きしたり、身体を温めたりする火もね
 」
」「お前の言うとおりだ」コヨーテは稲妻
 から火をとって、人々に与え、みんな大喜びした
から火をとって、人々に与え、みんな大喜びした
「ついでに人間には、弓矢や槍を与えてやれば、もっとうまく狩りができると思うんだけれど。
だけどね、兄貴、武器をやるのは人間だけで、動物には禁物だよ。
動物は動きが速い。大きな爪や歯、恐ろしい角をすでに持っている。ところが人間は動きがのろい。
その上、歯や爪も決して強くない。だから、もし動物がこの上、弓矢を持ったら、人間はとても生き残れねえよ」
「なるほど、弟よ、お前はすべてによく頭が回るやつだ。これでいいかい?」
「いや、いや、とんでもねえ。まだあるね。人間の言葉は今ひとつしかない。
人間は、自分と同じ言葉を喋る相手とは戦はできねえ。だから敵が必要だ。戦が必要だ」
「戦だって? そんなのなんの役に立つんだい?」
「戦はいいもんだよ。あんたは顔を朱色の絵の具でくまどる。出陣し、立派な手柄をたてる。
村の美しい若い娘を見つめると、彼女らも熱っぽく見つめかえすって寸法だ。
敵の馬
 や、妻や、娘をかすめ取る。金持ちになる。みんなはあんたを褒め称えて、あんたはもうピカンピカンだ
や、妻や、娘をかすめ取る。金持ちになる。みんなはあんたを褒め称えて、あんたはもうピカンピカンだ 」
」「シラペ。お前の言うことはまことに的を射ている」
そこでコヨーテじいさんは、ヒトをいくつもの部族に分けて、違った言葉を与えた。
すると実際、いたるところで戦争


 が起こり、戦功を讃える歌声が轟いた。
が起こり、戦功を讃える歌声が轟いた。「他人の女房を盗むって、あれは実にいいもんだ。俺たちの部族でも、妻の寝取り合いの習慣が続いている。
ところで弟よ、もしお前の女房が、もう一度お前のところへ戻ってきたら、彼女を家に入れてやるかね?」
「とんでもねえ! 俺にだって誇り、自尊心ってものがある!」
「シラペよ、お前はほんとに馬鹿もんだ。ものの道理ってものが分かっちゃおらん。
俺の女房は、3度も他の野郎にさらわれた。けれど帰ってくるたび、俺は家に入れてやった。
だから今では、なにかを命令すると、いつもあいつは、昔さらわれたことを思い出す」
そういうわけで、昔クロー族の間では、家族間に女房の盗み合いが盛んに行われ、
いったん別れた妻が帰ってきた時、平気で受け入れるのも、もとをただせば、
あのコヨーテじいさんまでさかのぼる、というわけなのです。
(どうも、後半が気に食わないなぁ・・・性の自由っていうなら分かる気もするけど

【訳注】
コヨーテは、アメリカ狼のことだが、アメリカ・インディアンの民話や詩には、最も魅力的な文化ヒーローとして頻繁に登場する。
神通力を持っていて、ヒトや他の動物をよくペテンにかけるが、自分も失敗して酷い目に遭うことが多いw
他のインディアンの「トリックスター」、ウサギ
 、カラスなどのように、
、カラスなどのように、ヒトや自然が織りなすリアリティの上に行使された喜劇的な想像力の産物は、ヒトすべてに共通する意識で、
コヨーテが象徴する「破壊性」や「論理的非一貫性」は、西欧近代社会が価値を置いてきた「秩序」とは、本質的に相容れないものではなく、
むしろ社会を活性化するのに役立つと、文化人類学的解釈によって、近年ますます人気が増している。
(どこかで、そんな風なことを読んだな。協調性のないような人がいると、案外突飛なアイデアを出して、組織を活発化させる、みたいな
【訳注2】
「笑いはそれ自体、宗教的言語の古い形態だ」(ジェローム・ローゼンバーグ)
シャーマンは薬がヤカンの中で煮えている間、儀式用の「吹管(ブローパイプ)」を吹かしながら詩を唱える。
「トータル・トランスレーション」(インディアンの口承詩の持つ、聴覚的・視覚的要素をトータルに捉えたローゼンバーグの試み)
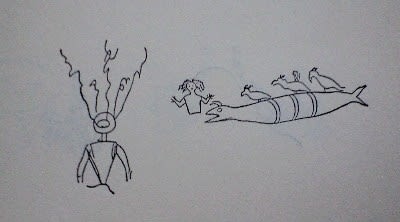
**************************白人侵入後
「アメリカへいちばん早く来た私たちは、いちばん遅く、やっと1921年にアメリカ人になった」(レスリー・マーモン・シルコー)
「おれの若者たちは働いてはいけない」
おれの若者たちは働いてはいけない
働く男は夢を見ることができないからだ。そして最高の知恵は夢の中で授かる。
君たち白人は、俺に土地を耕せという。
君たちは俺にナイフをとって母なる大地の乳房を切り刻めというのか。
そんなことをすれば俺が死んだ時、母は俺をその胸に抱きとり休ませてはくれないだろう。
(中略)
君たち白人の法律は悪い法律だ。俺の民はそんなものに従うことはできない。
俺は俺の民がここに、俺と一緒にいつまでもいてほしいのだ。
すべての死んだ仲間は、再び生を得るだろう。
俺たちは俺たちの父祖の家に留まり、俺たちの母のからだの中にいる彼らに再会する日を待たねばならない。
【訳注】
北米大陸に渡来した白人は、白人式に働くことを拒むインディアンを“救いがたい怠け者”と考えていた。
天才的科学者で進歩主義の権化のようだったベンジャミン・フランクリンの手紙によると、
アメリカ植民地にあるイギリス政府がインディアン連邦に対して、彼らの有望な子弟を預かり、
英国費で大学に入れ、西欧風に教育してやろうと申し出をした際、連邦側の反応をこう書いている。
「われらの子弟の何人かがすでに以前その大学で教育を受けたが、まったく無能者になっていた。
鹿を殺したり、ビーバーを捕えたりする方法を会得するまでに長年を要するていたらく。
しかしながら、英国の申し出は、連邦に対する好意と親善とみなし、感謝をこめた返礼をするにやぶさかではない。
もし英国側の紳士らの子弟をオノンダゴまで送ってくれれば、私たちは喜んで彼らの教育を引き受け、
真に最善の方法で彼らを一人残らず立派な男に仕立て上げてしんぜよう」(痛快だね

フランクリンはこう言った。
「インディアンたちにラム酒
 さえ与えれば、北米大陸からすべての野蛮人を掃蕩することができるだろう」
さえ与えれば、北米大陸からすべての野蛮人を掃蕩することができるだろう」その基本的態度は、極めて政治的、外交的で、「野蛮人を見下す文明人」だったことは間違いない。
白人たちが16C、北米大陸に殖民をはじめて以来、インディアンは様々な形で白人文明と接触し、
最後には「ウンデッド・ニーの惨劇」に終わった歴史がある。
とくに中西部、西部開拓が、もっとも強引に進んでいった。19Cに起こった白人文明の西進運動は、
インディアンの「聖なる土地」に決定的な圧力をかけた。
インディアン
 白人だけでなく、インディアンの部族同士の紛争も激化した
白人だけでなく、インディアンの部族同士の紛争も激化した


部族同士を相克させることで絶滅をはかる一方、間接的な破壊的手段も持っていた。
伝染病(はしか、天然痘、性病)、鉄砲、ラム、ウイスキー、キリスト教(彼らの伝統的な神話や世界観を破壊した)など。
「冬の啓示」(ダコタ・インディアン)(抜粋)
白人は神の四つの黒い旗があることを知っている。それは大地の四つの要素なのだ。
わたしこそ、鷲の女だ。わたしは女だから、この神の家に血を流すことには同意できない。
長い年月の後、お前は白人と一緒に暮らすようになるからだ。
インディアン娘ポカホンタスとのロマンスで有名なキャプテン・ジョン・スミスのスピーチ。
「愛をもってすれば得ることができるかもしれないものを、なぜ君たち(イギリス人植民者)は力によって強奪しようとするのか。
君たちに食物を分けてあげいるオレたちを、なぜ君たちは滅ぼそうとするのか。戦によって何が得られるというのか。
オレたちには武器がない。それに、もし君たちが友好的な態度で来るなら、喜んで欲しいものを分けてあげると言っているのだ。
美味い肉を食べて安眠し、自分の女や子どもと平和に暮らし、イギリス人たちとも楽しく笑って友だち付き合いをし、
イギリス人の銅器と、オレたちの斧を交換し合って生きるほうが、彼らから絶えず逃げながら暮らす生活よりもはるかに好ましい。
オレはそのくらいなことが分からないほどの大馬鹿だろうか。
まず銃や剣を捨てなさい。それこそが、オレたちの妬みの元なのだから。
さもなくば、君たちがおれたちを殺すのと同じ方法で、君たちも亡びるだろう」
とくに初期開拓者は、清教徒的感覚から、インディアンを、キリスト教に敵対する「悪魔の化身」と見ていた。
白人の彼らに対する恐怖と敵意の激しさは、言葉に尽くせないものだった。
その心理の半面は、有色人種に対する積年の「白人優越主義」が働いていた。
シャイアン族の「白かもしか(ホワイト・アンテローブ)」と言われた隊長も、1864年の「サンド・クリークの大虐殺」で戦死した。
彼は、弾丸を受けて地に倒れる直前、腕を組んで大地に立ったまま、この歌を詠んだという。
「白かもしかの歌える死の歌」
すべてのものは亡びる
すべてのものは亡びる
すべてのものは亡びる
大地と山々のほかは
この虐殺後、白人兵は彼の陰嚢を切り取りタバコ入れを作ったという。
(ヒトはそれほど冷酷になれるものか。狩った動物の剥製を飾って楽しむようなものか
 「ゴースト・ダンス」
「ゴースト・ダンス」インディアンたちは戦においても屈服しなかったが、文学においても、白人を神話と伝説の中にやがて組み込んでしまう。
最もユニークなものは「ゴースト・ダンス」の歌だろう。
「ゴースト・ダンス」とは、19C末に起こったインディアンの一種の宗教的民族主義運動だった。
だが皮肉にも、まったく異質のキリスト教の影響を受けた、救世主再臨を願う「リヴァイヴァリズム運動」でもあった。
この中心的な信仰は“いずれこの現世は亡びるだろう。だがいつか救世の神が現れて、救いが到来する”。
この最初の預言者は、デラウエア族のシャーマンだった。
もしインディアンが、白人社会の物質主義を排して、本来の生き方に専念したら、いずれ白人らはこの大陸を去るだろうと予言した。
最も有名なリーダーの一人「ハンサム・レーク」は、彼らの渇仰を集めた。
しかし、彼らが信じた真の「救世主」は、パイユート族のウォヴォカだった。
「すべてのインディアンがゴースト・シャツを着て、そのダンスを踊れば、野牛が地から立ち上がり、
夢の中で白人を踏み殺し、すべての鳥や獣が帰ってきて、アメリカの土地は、すべてインディアンの手に戻るはずだ」
すべてのインディアンが、白人の絶滅を信じたのである。
「ゴースト・ダンス」は、一種の恍惚、夢に入った踊り手が、その中で受け取る歌を歌う儀式だった。
これは、本来は平和的なものだった。一部を除けば、白人に直接戦闘を挑む者はいなかった。
精神的なレジスタンス運動だったが、これに苛立った一部のアメリカ政府軍は、明らかに防備の劣ったインディアン部落を急襲し、
婦女子を含む200人のスー族を殺した。1890年12月29日「ウンデッド・ニー」の事件だった。
 「ゴースト・ダンス」の詩
「ゴースト・ダンス」の詩「わたしは彼らに果物をやった」
子どもたちよ はじめわたしは白人たちが好きだった
わたしは彼らに果物をやった
わたしは彼らに果物をやった
父よ きいてくれ
わたしの咽喉はカラカラだ
わたしの咽喉はカラカラだ
ここにはもうなんにもない
ひとかけらの食べ物も
【訳注】
これらは文学的には、他の詩と較べて少し質が落ちるかもしれないが、
「おれたちはよみがえるぞ(ヒ・ニスワ・ビタニキ)」という彼らの声は、
インディアンはもちろん、白人の耳にも残響が続いている。
ベトナム戦争がたけなわな頃に、ゲイリー・スナイダーはこう書いた。
「アメリカ・インディアンとは、悩めるアメリカ人の心の奥に潜んでいる復讐に燃える幽霊なのだ。
だからこそ我々は、あれほどの残忍と情熱をもって、しかし心の中ではひどく混乱しながら、
“ベトコン”という髪の黒い若い農夫や兵士を殺している」
「白人はおれに貯えろと言う」(フレッド・レッド・クラウド)
白人はおれに言う
貯えろと
そこでおれは貯える
紐や 煉瓦や 木や馬や 革などを
ところがだれひとり
おれが貯えたものなどほしがらない
そこでおれは砂漠へ行って 直径四尺もある
おれが貯えた紐の玉をころがしてみる
そこへ やってきたのが白人二人
おれが貯えた煉瓦や 木や 馬や
革や 紐を そいつらは見る
そして おれに訊ねていわくには
おまえ そんなもの いったいどこで盗んだのだい?
おれの弁解なぞ 聞く耳もたぬと
やつらは 紐をおれから取りあげる
そしてそいつを
ロープに編んで
こんどはそれを
おれの首に巻きつける
そしておれがせっかく貯えた木の枝から
おれを吊るし首にしたんだとさ
「盗人」
おれたちは兵士だったから
戦争の意味は知っていた
勝ったほうが全部取るのだ
おれたちは外交官だったから
嘘の意味は知っていた
といってたいしておえら方じゃなかったけれど
おれたちは民主党だったから
政治の意味は知っていた
人間は人間だ
きみたちはおれたちの土地を盗(と)った
おれたちはそういうきみたちを 理解しようとした
だがきみたちはそこに住みついただけで その土地を愛さなかった
わが友よ
(たしかにきみたちなりの友情でもって、しばしばきみたちはおれたちのよき友であった)
だがそれにしてもわが友よ
いったいどういうわけできみたちは
おれたちの子どもの口元から
あのほほえみを盗んだのかね?
最後に現役インディアン作家レスリー・シルコーの美しい詩の終わりの数行をあげておく。
インディアン詩の伝統精神は、今もこうして脈々と続いているのだ。
「太平洋への祈り」
3万年前
巨大な海がめにまたがって

インディアンは 海原こえてやってきた
その日 波は高かった
大きな海がめたちは 灰色に煙る日暮れの海から
ゆっくりと這い上がってきた
祖父がめは 砂のなかで 四度ころがって
太陽のなかに泳ぎ入り
消えていった
そういうわけで
その昔から
老人たちも言うように、
海からの贈り物 雨雲は
西の方から漂ってくる
風に舞うみどりの木の葉
中国から ずっとやってきた
雨を呑みこんで
わたしの足の 濡れた土
**************************あとがき
拙著『アメリカ・インディアンの詩』(中公新書 1977年刊)が絶版になった。
それを思潮社が出してあげてもいいと言ってくれた。
子守唄など詩を増やし、トリックスターの話を2、3入れた。
【註】
ホピ族のコトバには「性別(ジェンダー)」が存在しない。
ホピ語の名詞は、無生物でも明らかに「生きたもの」として取り扱われている。