■ドラマ『顔』(2003)
原作:横山秀夫
出演:仲間由紀恵、オダギリジョー、京野ことみ、海東建、品川祐、益岡徹、余貴美子、田中哲司 ほか
第1話はこちら。
似顔絵担当の捜査官を通して、警察内の女性蔑視や、児童心理について描いてるのが興味深い。
![]()
![]()
広報課・小松浩二役。いつも隣りの女の子と一緒に平野巡査に嫌味を言ってる![]()
●第2話 目立ちたがる容疑者
銀行強盗の訓練中、ほんとうの強盗事件が発生。
広報のために写真撮影していた平野は、監察官に呼び出され交際関係まで聞かれる。
銀行にも犯人の顔を覚える担当がいるんだ/驚 訓練が10分遅れたのを知ってるのは署内の人間?
西島はカウンセラーから過去3件の暴力沙汰で異動になったことを指摘される。
「警察はただでさえ女のいる場所なんてないのに、マスコット的な存在が終わったら、あとはまるでお荷物扱いよ。
努力して昇進したって扱いは変わらない」
警察内に記者が集まる部屋があるんだ/驚
これって囚人のジレンマってやつ?
広報は捜査の手伝いをしたら処分なのか?![]()
●第3話 裏切られた愛を告発する似顔絵
地下道でヤミ金の男とモメて刺した若い男を、通りかかった母娘が目撃。
平野のあとを継いで似顔絵を担当している三浦が、やけに具体的な絵を描いたことに不審を抱く平野。
平野は以前、誘導尋問で捕まった犯人の似顔絵を描き直せと命令されて描けず、責任をとらされて左遷させられた。
「私たち女性警察官は今まで都合のいように使われてきたの。
“婦警ふぜいが”と言われて重要な仕事から外されてきた」
犯人を逮捕するのが優先で、似顔絵は手段のひとつってのも一理あるが。
「女性警察官は組織のオモチャじゃない、道具じゃないんです。心だってあるし、傷つきます」
差し入れのおむすびデカすぎ![]() ! フットボールくらいあった。平野は最初から暗い性格じゃなかったのか。
! フットボールくらいあった。平野は最初から暗い性格じゃなかったのか。
捜査で描く似顔絵は、デッサン力だけではなく、目撃者から特徴を丁寧に聞いて描くことが重要。
●第4話 死刑囚の証言
マンションで野上という女性が窒息死し、死体には赤ペンで暴言が書かれてた。16年も同様の事件があり、迷宮入りしている。
「犯人はオレだ」などイタズラ電話が殺到し、手伝いにまわされる平野![]()
死刑囚のヤナギが「犯人を知ってる」と証言。平野は似顔絵を描くよう言われる。
「似顔絵は、目撃者と描く者との信頼関係で成り立っているんです」
描いたのは若い女性。絵にソックリな飯田という美容師が浮かび上がる。
関内でまた若い女性が襲われ、被害者はまだ生きてた。飯田にはアリバイあり。
「婦警さん、あんたの腕は本物だ。死ぬ前にもう一度娘に会えた」泣かせるねえ。
記者「世間が喜ぶのは、非情殺人とスキャンダル」て、ほんと昔から人気だよね。
平野のナース姿サービスショットありv
●第5話 封印したはずの昔の顔
3人組による強盗事件。
平野は、検挙率NO1、県警に誘われても異動しないというカジマ刑事の特集取材を任される。
婦警は今度は尾行のカップルを装う道具か![]()
カジマは犯人の1人に刺される。「青い鳥」とは? 12年前の大きな事件と関係あり?
西島は幼少時代のトラウマがよみがえる。
●第6話 完全犯罪を狙う犯人の素直な自白
![]() 秘密の曝露:犯人しか知り得ない事実
秘密の曝露:犯人しか知り得ない事実
山でナイフが発見された。そのスクープを東都日報が報じた。連日のスクープに内部の情報漏えいではと不信感を抱く上司。
平野は東都日報の内村記者を見張るよう命令される。
射撃で準優勝となった神埼は、捜査一課に異動になったが、電話番![]() 、お茶汲み
、お茶汲み![]() 、コピーとり。
、コピーとり。
神埼と内村の2ショットがメールで流れる。
●第7話 愛する者たちを引き裂く一発の銃弾
神埼は特練の帰り、警官に職質して襲われ、拳銃を奪われた。婦警に銃を携帯させる決定が下ったばかり。
神埼は体中を殴られ重体。平野は神埼の代わりに捜一に貸し出され、ミノダ(佐野)刑事の下につく。
「これだから女は使えねんだ」
自分の名前の入った肖像画に誘われて入った美術商は元鑑識課で似顔絵を描いていた。
平野は施設で育った孤児。
絵を買うという女性の話から、描いたのは平野の父、描かれているのは母かもしれない?
神埼の意識が戻り、犯人は警官の格好をした女・鈴木。
あんなマニアックな店あるんだ![]() 本物の警察手帳はどこで手に入れたんだ???
本物の警察手帳はどこで手に入れたんだ???
マニアック店員・芥川に撃たれて階段落ちした西島。改造拳銃だった。
佐野さんが刑事って怪しすぎ![]()
●第8話 運命の再会
「いつかなんてないんだよ。やりたいことがあるなら今やらないと、後回しにしてたら後悔する」
平野は、昔から自画像が描けない。自分の顔が見えないという。
鈴木は女性を蔑視している男性化した人物ではないか。署内のカウンセラーはプロファイリングもやるのか。
「後悔なんてするやつは何やってもするし、しないやつは何やってもしない」て納得。
絵の女性は三浦あかねというキリスト教信者。心臓が弱く、ミズホを預けた日に亡くなった。
母は夫を亡くし、自分の余命を知って教会に預けた。
「何のために必死に働いてきたのか」てここでも『シングルマザー』と同じセリフ。
「家があっても、物に恵まれてても、きっと奥さんは心の奥で寂しかったんじゃないですか?
ミノダさんもそれに気づいてて放っておいた。自分の問題と向き合うのは辛いですよね」
西島は、少年のころ、母親が殺されるのを見ていた。
オダジョーは包帯巻いててもイケメンヘアスタイル。
●第9話 操られた記憶
連続通り魔事件の目撃者捜索チラシを3週間も配ってるのも婦警か![]()
工事現場で見たという情報が入る。また昔の記憶がよみがえって、犯人・園田を必要以上に殴ってしまう西島。
園田は白川事件だけ自白しない。外傷性の記憶障害だった白川の見た犯人の顔はやはり園田。
白川はピアニストだったが、ピアノが怖いと処分されていた。
![]()
あれ!?オダジョーがCD聴いてるデッキ、ウチのと同じだ![]()
てか、私どんだけ物もちがいいんだ![]()
●第10話 19年前の真相を知る者
母親が殺されたところを目撃した娘を見て、西島の様子もおかしくなる。
少女は精神的ショックで声が出なくなり、幼児退行してしまった。
平野は、結婚したての友人ミカの家を訪ねると、夫からDVを受けていてミズホも怪我を負う。
カウンセラー樋口の自宅に盗まれた宝石が送られてきた。
また強盗事件が起こり、19年前の事件と同じ首の圧迫跡。片手は義手。西島の母と同一犯か?
平野は、西島を説得して同一犯かもしれない男の似顔絵を描く。
●最終話 もう一つの顔に逢える
盗品のネックレスを送ってきたのは、昔の樋口の患者・片岡。
うまくさばかないと昔の犯罪をバラすと脅されていた(セキュリティのある玄関をどうやって入ってきたの?![]()
片岡は19年前の犯行を告白する。殺人の時効は15年。
片岡のことを知った西島を追うと、ドリルで腹に穴があいた片岡のそばに血まみれの西島がいた。
記者は、なんでも名前公表して書いても怒られないんだっけ?![]()
外国ならすぐ名誉毀損で訴えられるよね。
鶴さん役の俳優さんはいつもイジワルな役だね![]()
「ほんとうに殺したかったのは自分じゃないんですか? お母さんを守れなかった自分を」
少女アヤノの声が出て、犯人は片岡じゃないと分かる。
![]() 記憶のすり替え:強烈な体験をすると一番印象深いものが記憶されて、それが主に出てくるようになる。
記憶のすり替え:強烈な体験をすると一番印象深いものが記憶されて、それが主に出てくるようになる。
松重さん、ヤヴァい![]()
![]() 共同正犯:二人以上が共同して犯罪を実行した場合の実行者をいう。
共同正犯:二人以上が共同して犯罪を実行した場合の実行者をいう。
「この世に顔のない奴なんていないんだよ。認めたくないだけで」
「この世で一番辛いことは自分の顔を知ることかもしれない。でも、それを知った時から本当に生きていけるんだと思います」
原作:横山秀夫
出演:仲間由紀恵、オダギリジョー、京野ことみ、海東建、品川祐、益岡徹、余貴美子、田中哲司 ほか
第1話はこちら。
似顔絵担当の捜査官を通して、警察内の女性蔑視や、児童心理について描いてるのが興味深い。


広報課・小松浩二役。いつも隣りの女の子と一緒に平野巡査に嫌味を言ってる

●第2話 目立ちたがる容疑者
銀行強盗の訓練中、ほんとうの強盗事件が発生。
広報のために写真撮影していた平野は、監察官に呼び出され交際関係まで聞かれる。
銀行にも犯人の顔を覚える担当がいるんだ/驚 訓練が10分遅れたのを知ってるのは署内の人間?
西島はカウンセラーから過去3件の暴力沙汰で異動になったことを指摘される。
「警察はただでさえ女のいる場所なんてないのに、マスコット的な存在が終わったら、あとはまるでお荷物扱いよ。
努力して昇進したって扱いは変わらない」
警察内に記者が集まる部屋があるんだ/驚
これって囚人のジレンマってやつ?
広報は捜査の手伝いをしたら処分なのか?

●第3話 裏切られた愛を告発する似顔絵
地下道でヤミ金の男とモメて刺した若い男を、通りかかった母娘が目撃。
平野のあとを継いで似顔絵を担当している三浦が、やけに具体的な絵を描いたことに不審を抱く平野。
平野は以前、誘導尋問で捕まった犯人の似顔絵を描き直せと命令されて描けず、責任をとらされて左遷させられた。
「私たち女性警察官は今まで都合のいように使われてきたの。
“婦警ふぜいが”と言われて重要な仕事から外されてきた」
犯人を逮捕するのが優先で、似顔絵は手段のひとつってのも一理あるが。
「女性警察官は組織のオモチャじゃない、道具じゃないんです。心だってあるし、傷つきます」
差し入れのおむすびデカすぎ
 ! フットボールくらいあった。平野は最初から暗い性格じゃなかったのか。
! フットボールくらいあった。平野は最初から暗い性格じゃなかったのか。捜査で描く似顔絵は、デッサン力だけではなく、目撃者から特徴を丁寧に聞いて描くことが重要。
●第4話 死刑囚の証言
マンションで野上という女性が窒息死し、死体には赤ペンで暴言が書かれてた。16年も同様の事件があり、迷宮入りしている。
「犯人はオレだ」などイタズラ電話が殺到し、手伝いにまわされる平野

死刑囚のヤナギが「犯人を知ってる」と証言。平野は似顔絵を描くよう言われる。
「似顔絵は、目撃者と描く者との信頼関係で成り立っているんです」
描いたのは若い女性。絵にソックリな飯田という美容師が浮かび上がる。
関内でまた若い女性が襲われ、被害者はまだ生きてた。飯田にはアリバイあり。
「婦警さん、あんたの腕は本物だ。死ぬ前にもう一度娘に会えた」泣かせるねえ。
記者「世間が喜ぶのは、非情殺人とスキャンダル」て、ほんと昔から人気だよね。
平野のナース姿サービスショットありv
●第5話 封印したはずの昔の顔
3人組による強盗事件。
平野は、検挙率NO1、県警に誘われても異動しないというカジマ刑事の特集取材を任される。
婦警は今度は尾行のカップルを装う道具か

カジマは犯人の1人に刺される。「青い鳥」とは? 12年前の大きな事件と関係あり?
西島は幼少時代のトラウマがよみがえる。
●第6話 完全犯罪を狙う犯人の素直な自白
 秘密の曝露:犯人しか知り得ない事実
秘密の曝露:犯人しか知り得ない事実山でナイフが発見された。そのスクープを東都日報が報じた。連日のスクープに内部の情報漏えいではと不信感を抱く上司。
平野は東都日報の内村記者を見張るよう命令される。
射撃で準優勝となった神埼は、捜査一課に異動になったが、電話番
 、お茶汲み
、お茶汲み 、コピーとり。
、コピーとり。神埼と内村の2ショットがメールで流れる。
●第7話 愛する者たちを引き裂く一発の銃弾
神埼は特練の帰り、警官に職質して襲われ、拳銃を奪われた。婦警に銃を携帯させる決定が下ったばかり。
神埼は体中を殴られ重体。平野は神埼の代わりに捜一に貸し出され、ミノダ(佐野)刑事の下につく。
「これだから女は使えねんだ」
自分の名前の入った肖像画に誘われて入った美術商は元鑑識課で似顔絵を描いていた。
平野は施設で育った孤児。
絵を買うという女性の話から、描いたのは平野の父、描かれているのは母かもしれない?
神埼の意識が戻り、犯人は警官の格好をした女・鈴木。
あんなマニアックな店あるんだ
 本物の警察手帳はどこで手に入れたんだ???
本物の警察手帳はどこで手に入れたんだ???マニアック店員・芥川に撃たれて階段落ちした西島。改造拳銃だった。
佐野さんが刑事って怪しすぎ

●第8話 運命の再会
「いつかなんてないんだよ。やりたいことがあるなら今やらないと、後回しにしてたら後悔する」
平野は、昔から自画像が描けない。自分の顔が見えないという。
鈴木は女性を蔑視している男性化した人物ではないか。署内のカウンセラーはプロファイリングもやるのか。
「後悔なんてするやつは何やってもするし、しないやつは何やってもしない」て納得。
絵の女性は三浦あかねというキリスト教信者。心臓が弱く、ミズホを預けた日に亡くなった。
母は夫を亡くし、自分の余命を知って教会に預けた。
「何のために必死に働いてきたのか」てここでも『シングルマザー』と同じセリフ。
「家があっても、物に恵まれてても、きっと奥さんは心の奥で寂しかったんじゃないですか?
ミノダさんもそれに気づいてて放っておいた。自分の問題と向き合うのは辛いですよね」
西島は、少年のころ、母親が殺されるのを見ていた。
オダジョーは包帯巻いててもイケメンヘアスタイル。
●第9話 操られた記憶
連続通り魔事件の目撃者捜索チラシを3週間も配ってるのも婦警か

工事現場で見たという情報が入る。また昔の記憶がよみがえって、犯人・園田を必要以上に殴ってしまう西島。
園田は白川事件だけ自白しない。外傷性の記憶障害だった白川の見た犯人の顔はやはり園田。
白川はピアニストだったが、ピアノが怖いと処分されていた。

あれ!?オダジョーがCD聴いてるデッキ、ウチのと同じだ

てか、私どんだけ物もちがいいんだ

●第10話 19年前の真相を知る者
母親が殺されたところを目撃した娘を見て、西島の様子もおかしくなる。
少女は精神的ショックで声が出なくなり、幼児退行してしまった。
平野は、結婚したての友人ミカの家を訪ねると、夫からDVを受けていてミズホも怪我を負う。
カウンセラー樋口の自宅に盗まれた宝石が送られてきた。
また強盗事件が起こり、19年前の事件と同じ首の圧迫跡。片手は義手。西島の母と同一犯か?
平野は、西島を説得して同一犯かもしれない男の似顔絵を描く。
●最終話 もう一つの顔に逢える
盗品のネックレスを送ってきたのは、昔の樋口の患者・片岡。
うまくさばかないと昔の犯罪をバラすと脅されていた(セキュリティのある玄関をどうやって入ってきたの?

片岡は19年前の犯行を告白する。殺人の時効は15年。
片岡のことを知った西島を追うと、ドリルで腹に穴があいた片岡のそばに血まみれの西島がいた。
記者は、なんでも名前公表して書いても怒られないんだっけ?

外国ならすぐ名誉毀損で訴えられるよね。
鶴さん役の俳優さんはいつもイジワルな役だね

「ほんとうに殺したかったのは自分じゃないんですか? お母さんを守れなかった自分を」
少女アヤノの声が出て、犯人は片岡じゃないと分かる。
 記憶のすり替え:強烈な体験をすると一番印象深いものが記憶されて、それが主に出てくるようになる。
記憶のすり替え:強烈な体験をすると一番印象深いものが記憶されて、それが主に出てくるようになる。松重さん、ヤヴァい

 共同正犯:二人以上が共同して犯罪を実行した場合の実行者をいう。
共同正犯:二人以上が共同して犯罪を実行した場合の実行者をいう。「この世に顔のない奴なんていないんだよ。認めたくないだけで」
「この世で一番辛いことは自分の顔を知ることかもしれない。でも、それを知った時から本当に生きていけるんだと思います」

 には、マリーゴールド財団役員のミズ・マクファーレンが所有する
には、マリーゴールド財団役員のミズ・マクファーレンが所有する 、森などの自然豊かな風景に一変して、
、森などの自然豊かな風景に一変して、 /驚
/驚














 がのっかってるw
がのっかってるw







 があるんですか?」てw “heaven call”ていいこと言うね。
があるんですか?」てw “heaven call”ていいこと言うね。


















 もいただろう。
もいただろう。 ウシガエル:食用として持ち込まれた。
ウシガエル:食用として持ち込まれた。 ミシシッピアカミミガメ:ペットとして持ち込まれた→もとから棲んでいるカメの住処を奪ってしまう。
ミシシッピアカミミガメ:ペットとして持ち込まれた→もとから棲んでいるカメの住処を奪ってしまう。
 ・ねこ
・ねこ の写真でも大人気な岩合さんの本。
の写真でも大人気な岩合さんの本。



 驚×5000
驚×5000









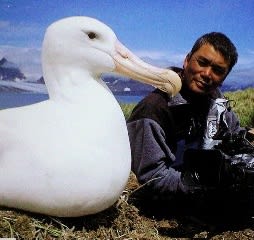





 、携帯
、携帯
 が増えた結果として砂漠が広がっている。
が増えた結果として砂漠が広がっている。




 に覆い尽くされてしまうだろう。
に覆い尽くされてしまうだろう。




 がゾウガメの卵を食べ、
がゾウガメの卵を食べ、

 をかけ合わせてつくらるラバ。
をかけ合わせてつくらるラバ。


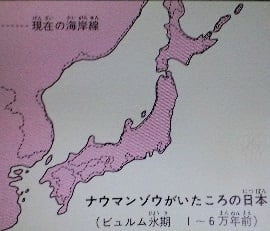












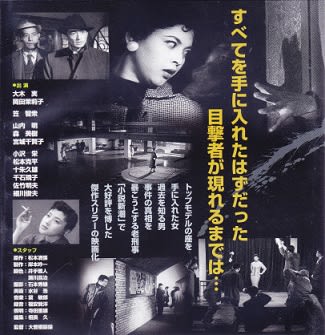





 、岸田今日子 ほか
、岸田今日子 ほか



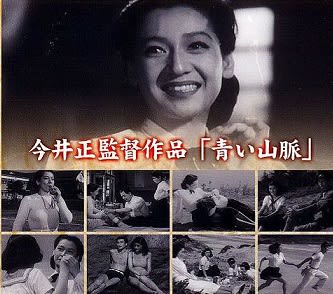
 でこの騒ぎになっちゃうんだから改革って大変!!
でこの騒ぎになっちゃうんだから改革って大変!!





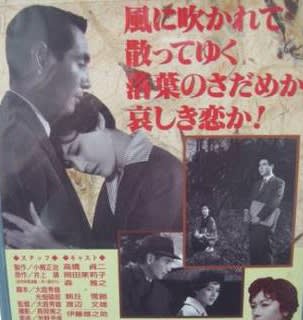














 これを一番ステキに見せたいと決めたら、それに合わせてコーディネートするべし!
これを一番ステキに見せたいと決めたら、それに合わせてコーディネートするべし!
 」と差別発言したことでヒンシュクを買う。
」と差別発言したことでヒンシュクを買う。
 !?
!?






 呑み屋コーナー。
呑み屋コーナー。





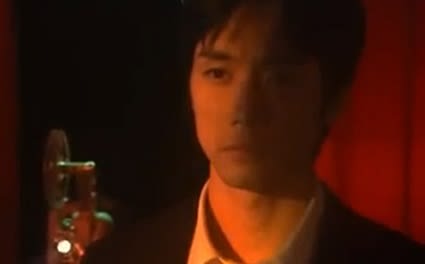













 の知識だけでなく、英語やフランス語などの語学力、サービスの仕方なども審査された。
の知識だけでなく、英語やフランス語などの語学力、サービスの仕方なども審査された。





