■
『ノーザンライツ』(新潮社)
星野道夫/著
******************************郵便配達人~ヘイリー・ティケット
セスの小さい頃の話。
昔、ヘイリーの奥さんがアンブラー村の郵便局の仕事をしていて、
冬になるとセスの父はまったく村には行かなくなるから、小さな小屋が我が家の郵便物で一杯になる。
ヘイリーの狩猟への想いが重なると、犬ゾリでついでに持ってきてくれるのさ。
ヘイリーは必ず父に聞いた「オオカミがやって来るかい?」
ある日、ヘイリーはスノーモービルでオオカミを追っている時、エンジンが止まってしまい、息絶え絶えに家にやって来たことがあった。
その後、父は一番優秀な2匹のリードドッグが亡くなり、犬ゾリへの興味を急に失った。
12、3歳の頃、ヘイリーの家に寄ると、白人の作るガラクタにいつも文句を言っていた。
テレビ、カセットデッキ、CBラジオ、コーラ・・・。
つい数ヶ月前、国立公園の人間がアンブラー村に来て、セスについていろいろ尋ねたらしい。
「ここは新しい国立公園の境界線の中に入っています。
この家は不法侵入ですので、私がいつでも火をつけて燃やせるリストに挙げられています。
もう21世紀なのですから、こんな暮らしは出来ないんですよ」
******************************最後の白人エスキモー~ドン・ウィリアムス
![]()
レインジャーをしていたドン
1960年。ドンはコバック川流域を訪れた。セスの父、ハウイ・キャントナー一家らとともに土のイグルーを建て、
狩猟だけによる原野の生活に入った。ドンは、マッキンレー国立公園のレインジャーだった。
1980年。星野さんは、ドンに初めて会う。
多くの若者が、原野の暮らしにあこがれて、この土地にやって来ては消えて行った。
極北の自然は歳月の中で彼らをふるいにかけ、素晴らしい理想さえもこぼれ落ちてゆく。
ある者は最初の冬で去り、ある者は何年かの貴重な体験を思い出を胸に町の暮らしへと戻ってゆくのだ。
コバック川流域に来た仲間の中でドンだけがこの土地に残された。
エスキモーのメアリーと家庭を持ったドンには、もう帰る場所がなかった。
![]()
人はいつの日かどこかで根を下ろさねばならないことを、ドンの憂いを秘めた笑顔はそっと教えてくれた。
セスにとって、ドンの一人息子アルヴィンはたった一人の親友だった。
アルヴィンは家庭を持ち、レッドドッグ鉱山で働いている。
現金収入の機会がないこの土地で、多くの若者たちが鉱山で働くことを夢見ていた。
「新しい時代との狭間で、エスキモーの若者たちはどうしていいかわからないんだ。
彼らだって変わってゆきたいのだと思う。だから仕事があるということは、きっといいことなんだよ」(セス)
アラスカはアメリカに残された最後のフロンティアだった。
1968年、北極圏の油田発見は、それを根底から変えていった。
壮大な原野の広がりは何も変わらないが、人々の心の中に、どうしても消し去ることができないラインが引かれていったのである。
アラスカの原野に散った開拓者たちは、その見えないラインによって閉め出されようとしていた。
そのラインは、エスキモーやインディアンの人々の土地に対する観念さえ変えつつあった。
太古から、土地は個人が所有するものではなく、ただそこに存在するものだった。
しかし、「アラスカ原住民土地請求権解決法」により、それぞれの土地所有権が決まった。
ある村人が、自分の土地で誰かが焚き木を切ったとこぼしていた話をドンは信じられない思いで語った。
誰もが、人生の中で、何かを諦め、何かを選びとってゆくのだろう。
アラスカもまた、人の一生のように、新しい時代の中で何かを諦め、何かを選びとってゆく。
******************************苦悩するグッチンインディアン~リンカーン
地平線をわずかに滑ってゆく束の間の太陽を見つめていると、可笑しな話だが、その愛おしさに心が満たされてくる。
「北極圏野生生物保護区における油田開発の問題」ほど、アメリカの環境保護運動の歴史の中で大きな論争はなかったかもしれない。
かつてアイゼンハワー大統領が、未来の世代のために残そうと指定した場所だった。
![]()
アメリカ中を揺るがした論争の中でさえ、グッチンインディアンの人々は忘れられ続けていた
リンカーン:グッチンインディアンの若きリーダー的存在の一人。星野さんの古い知人。
「オレたちの想いは、あなたたちの考えている自然保護とは少し違う。
オレたちは季節とともに通り過ぎるカリブーを殺し、カリブーと共に生きている。
自然は見て楽しむものではなく、存在そのものなんだ」
星野さんにとっても「野生生物保護区」は特別な土地だった。
カリブーの旅を“間に合って”見ることができた大切な世界。
狩猟民から見たカリブーの世界を追いたかった。
![]()
オールドクロウ村でのグッチンインディアンの集会
若者たちの伝統的文化の喪失、アルコール中毒、自殺、古老と若い世代のギャップ、未来への不安。
彼らの抱える問題が、そのまま僕たちの問題であるという驚きにとらわれた。
長い目で見れば、今抱えている問題も、次の時代へたどり着くための、通過しなければならない嵐のような気もしてくる。
一人の一生が、まっすぐなレールの上をゴール目指して走るものではないように、ヒトという種の旅もまた、
風向きを見ながら、手探りで進む航海のようなものではないだろうか。
「バッファローの大群は消えてしまったが、私たちはまだカリブーを救うことができる」
「大変な時代がやってくるだろうな」とリンカーンがつぶやいた言葉は忘れられなかった。
それは、グッチンインディアンだけでなく、私たちも含めた人間の時代という意味だった。
混沌とした時代の中で、私たちはある無力感に襲われる。それは正しい1つの答えが見つからないからである。
が、こうも思うのだ。正しい答えなどはじめから存在しないのだと。
しかし、その時代、時代で、より良い方向を模索してゆく責任はある。
あの集会で出会ったグッチンインディアンをゆっくり訪ねてみよう。
新しい時代の中でどう生きてゆこうとしているのか、もっとゆっくり耳を傾けてみよう。
![]()
******************************アラスカはだれのもの?
開発か自然保護かの選択は、人間が抱える環境問題の1つのシンボルとして、世紀末に生きる私たちに課せられた最後のテストのような気もする。
「1960年中ごろに開かれたNYのワールド商業フェアが大きな引き金になったかもしれない」(シリア)
「私たちが“アラスカ自然保護協会”を作ったのは1956年だった。最初の目的は、“北極圏野生生物保護区”のラインを地図上に引くことだった。
当時、アラスカは州に昇格したばかりで、資源開発による経済自立を目指しはじめていた」
「ワールドフェアで、伝統的な土地がアラスカは州政府議員によって売りに出されていたの、別荘にどうかって。
“州昇格法”によって、アラスカの1/3が州に委譲され、25年以内に具体的な土地の選択を行うよう定められた。
土地の選択が進むにつれ、原住民の“アボリジナル・ライト(原住民土着権)”と至る所で衝突していたの」
「原住民土着権」が定められたのは1867年。
“原住民は、現実に使用している土地の利用は妨げられないが、所有権を取得する条件は、将来の議会の立法に委ねる”という曖昧なものだった。
![]()
「ランパートダム計画」
ユーコン川のランパート渓谷に巨大ダムを築き、アメリカに500万kwの電力を供給する計画。
もしシリアらが中止活動をしなければ、多くの内陸インディアンの村々が水の底に沈んだだろう
![]()
1968年、プルードー湾に大油田を発見。
1971年、「原住民土地請求権解決法」ができ、原住民に4000万エーカーが与えられた代わりに、アボリジナル・ライトを放棄し、10億ドルが与えられた。
シリアは、アメリカでもっとも権威のある自然保護団体「ウィルダネスソサエティ」の女性初会長となり、ワシントンDCに移った。
会長を2年務め、フェアバンクスに戻り、地元の新聞『フェアバンクス・デイリーニューズマイナー』に週1回のコラムを書き始める。
「開発派が圧倒的で“反対意見って?”と聞き返した編集者の言葉を覚えているわ」
シリアの最初の記事に驚いた新聞社は、2回目以降、どんどん片隅に場所を変えていった。
シリアのコラムは今も続いている。
1980年、カーター大統領により「アラスカ国有地自然保護法」が成立。1億400万エーカーが国立公園、野生生物保護区になった。
カーターは大統領選に敗れ、共和党のレーガンの時代となる。
「100%の勝利なんて絶対存在しないのよ。
時代はいつも動き続けていて、人間はいつも、その時代、時代にずっと問われ続けながら、何かの選択をしなければならないのだから・・・」
![]()
ブッシュパイロットのドン・ロス
「アラスカの厳しい自然は観光客を寄せ付けないし、壮大なカリブーの旅を見るヒトもいない。
人々が利用できない土地なら、たとえどれだけ貴重だろうと、資源開発のために使うべきではないか」(ドン)
******************************「何かがおかしい」と見通す力~アークティックビレッジ
12月のフェアバンクスの太陽は、じれったいほどなかなか昇らない。
が、長い長い夜をへて現れる太陽に、人々は生かされているという温もりを感じ、人間の脆さに気づかされる
![]()
アークティックビレッジに行こうと思ったのは、歴史的な土地制度に唯一参加しなかったこの村を訪れてみたかったから。
二十数年を経て、理想的だと信じた土地制度は、さまざまな問題を生み出している。
個々が所有した広大な土地は、何の利益も生み出さないことで、目先の利益のために売られる危険性が出てきた。
アークティックビレッジは、連邦政府からの補助金を受け取らない代わりに、アメリカの資本主義経済に組み込まれることを拒否し、
「リザベーション(留保)」という自治権を獲得した。
オールドジョンレイクには、「カリブーフェンス」という19Cのカリブーの狩猟跡がある。
移動ルート沿いにV字状の巨大な木の柵をつくり、知らずに入ってくる獲物を槍や弓矢で殺す。
上空から見下ろすと、ナスカの地上絵のように白いV字が浮かび上がるという。
古老の話は、アラスカに対するぼくのイメージをゆっくりと変えた。
手付かずに残された、未踏の原野は、実はさまざまな人間が通り過ぎた、物語に満ちた原野だった。
![]()
トリンブル:村で尊敬される牧師
村人に「土地制度に参加しなくて良かったですか?」と聞くと、
「大切なのは、お金ではなくて、昔からの暮らしをこの土地で続けられるかどうかだからな」
「その判断はどう決めたのですか?」
「みんなで話し合って決めたのさ。未来の孫たちのことを考えると、なんとなく、それが一番いいような気がしたのさ」
「ヒトが生き延びるために一番大切なのは、自然に対する畏怖という感覚を持てるかどうかだと思う」
次の世代を担う人々と話していて感じるのは、村の古老が次々と世を去ってゆく悲しみと焦りだ。
大切な舵を失いながら、嵐の中の航海へ出てゆくような不安なのだろう。
先週この土地を去った90歳の老女の訃報は、アラスカ中のインディアンの村々を衝撃となって駆け巡った。
彼女は、最後のスピリチュアルリーダーの一人だったのだ。
******************************クリンギット族の寡黙な墓守~ボブ
![]()
ボブ
「エスキモーやインディアンだけでなく、白人だって新しい時代を迎えるだろうな。
もう何かが変わろうとしているよ。次の時代を背負う世代が少しずつ出てきているから」
目まぐるしく、加速度的に動き続ける時代という渦の中で、ぼくは新しい力が生まれつつあることを確信しはじめている。
それは、ただ“昔は良かった”という過去に立ち戻ることではない。
ノスタルジアからは何も新しいものは生まれてはこない。
自然も、ヒトの暮らしも、決して同じ場所にとどまることなく、すべてのものが未来へ向かって動いている。
「クリンギットインディアンにとって、デビルスクラブほど大切な薬草はない」(ボブ)
![]()
歳月の中で消えてゆく木の文化~トーテムポール
北アメリカとユーラシアが陸続きだった1万8000年前、干上がったベーリング海を渡り、
インディアンの祖先の最初の人々が北方アジアからアラスカにやって来た。
その中に、後にトーテムポールの文化を築いたクリンギット族がいる。
それは後世まで残る石の文化ではなく、歳月の中で消えてゆく木の文化だった。
そして多くの古いトーテムポールは、世界中の博物館に持ち去られていった。
ボブは10代の終わり~20代にかけてアラスカ中を転々とし、アル中、ドラッグ、ある種のアラスカ先住民の若者たちが陥る世界の中で、
一時は浮浪者にもなり、やがてフェアバンクスにやって来た。
1970年、さまざまな村から出てきたインディアンを差別視する警察との闘いは熾烈だったらしい。
ボブは逮捕され、すさまじいリンチを受け、フェアバンクスから追い出された。
ボブは古老たちから“人を許すこと”を学び、白人へ憎しみも消えていったという。
故郷の南東アラスカには、誰も見向きもしない古いロシア人墓地が住宅建設の場所となった。
だが、そこは千年以上にわたるクリンギットインディアンの墓地だった。
工事が始まり、人骨は投げ出され、埋葬品は盗まれた。
ボブは毎日一人で骨を土に戻していった。この行動が大論争を引き起こし、住宅建設はストップされた。
「ボブがあの墓を守ってから、この町のクリンギットインディアンの世界が少しずつ変わった。
とくに若者たちが自身のアイデンティティに目覚めていった。そしてとても自信を取り戻した」
アメリカ陸軍フェアバンクス分隊の小部隊が去年の秋から墓地の下草刈りを手伝っている。
“木も、岩も、風さえも、魂をもって、じっと人間を見据えている”
いつか聞いたインディアンの神話の一節をふと思い出していた。
******************************思い出の結婚式~アル・スティーブンス
アル・スティーブンス:アサバスカンインディアン。アラスカ大学の新学期に星野さんと出会って意気投合した。
「パイプラインができてからムースの数がめっきり減った。どうしたらいいのか、知りたかった」
アルと白人のゲイの結婚式。買い物に想像以上に時間がかかったが、人々は4時間も待っていてくれた。
翌日は快晴。こんな秋の日を「インディアンサマー」という。本当にいい式だった。
![]()
![]()
「アルカトラズ」
サンフランシスコ湾に浮かぶ小さな無人島。1969年、14人のインディアンの若者が上陸して、19ヶ月占拠した。
彼らは、この島が先祖から受け継いだ神聖な大地の一部だと訴えた。その中心人物がアルだと星野さんは知る。
「ミチオ、誰もが自分の人生を書きつづる力があったらいいだろうな。どんな人間も人生を語るに値するものだと思う。
とても時間がかかったけれど、白人に対する憎しみが消えてから、オレは生まれ変わったような気がする」
******************************ベトナム帰還兵・ウイリー
![]()
![]()
それぞれのクランの衣装をまとう村人/ウイリー
南東アラスカに約100年ぶりにトーテムポールが建てられた。
そこには、初めてワタリガラスとハクトウワシが一緒に刻まれた。
クリンギットインディアンの人々は、祖先の始まりを動物と信じ、それぞれの家系(クラン)の物語をトーテムポールに託した。
クランは大きくワタリガラスとハクトウワシに分かれ、さらにハイイログマ、シャチ、とさまざまに分かれてゆく。
21世紀を迎える現代も、人々はクラン同士の長い歴史の中で対立や怨念さえも生み出してきた
![]()
「ミチオ、明日漁に出るけど、一緒に行くか?」
「それ、ジャパニーズタイム? それともインディアンタイム?」
ジャパニーズタイムは、時間になっても来なければ行ってしまうこと、インディアンタイムは遅れてもいつまでも待ってくれること。
つまり時間通りになんて誰も現れないことだ。
ベトナム戦争
より多くの黒人が、より危険な前線に送られたように、エスキモーや極北のインディアンもまた同じ運命をたどった。
ベトナム戦争で、5万8132人の米兵が命を落としたが、戦後、その3倍の約15人の帰還兵が自殺したことはあまり知られていない。
ウイリーも首をつって自殺未遂を図ったが、7歳の息子が必死に支え続けたという。
10年以上前、ぼくはワシントンDC郊外の「ウォール(壁)」と呼ばれるベトナム戦没者慰霊碑を訪れた。
戦後、生きて帰った多くの若者が、「ポストベトナムシンドローム」という精神病に侵されていった。
![]()
セブンサークル
ジャコウウシの群れはオオカミに襲われた時、円陣を組んで、知恵のある年寄りが外側に立ち、一番内側にいる子どもを守る。
つまりオオカミは、ドラッグ、アルコール中毒、自殺、暴力、、、今の子どもたちが抱えている問題のこと。
セブンサークルは、そんな願いをもったグループ。
![]()
スウェットロッジ
スー族、ナバホ族などアメリカンインディアンに残る古い儀式。
自己の魂と出会うため、たった一人で何も食べずにヴィジョン・クウェストという旅に出る時、ここで身を清める。
私たちは裸になって焚き火
![]()
の周りに立ち、“シャチがやって来た”という古いクランの歌がうたわれた。
テントの中で輪になって座り、“火を守る女”によって焼けた石がテント内に運ばれる。
すり潰した薬草が回ってきて、祈りながら石にかけると、テント内はその匂いに満ちた。
「グランドファーザー・・・私は祈ります・・・聖なる大地、ストーンピープル、家族、ワタリガラスの魂のために・・・」
グランドファーザーは、なにか大いなる存在を意味しているのだろうか。
ぼくは意識が薄れる中で、人が祈るという姿に打たれていた。
人はいつも、それぞれの光を捜し求める、長い旅の途中なのだ。
******************************クジラとともに生きるエスキモー~エイモス
人々はただ自然に生かされているのである。
![]()
エイモスはポイントホープ村の次世代を担う男
星野さんは十数年ぶりにポイントホープ村を訪れる。
エイモスは荷物をスノーモービルに積みながら“ミチオがポイントホープに戻って来た”と独り言のように何度も呟いている。
21Cを迎えようとしている今、遥かなエスキモーの村のどの家にもテレビ、ガスのキッチンもある。
ぼくが立っていたのは、何百年、いや何千年も昔の土のイグルーで作られたポイントホープの住居跡だった。
ぼくはこの土のしたに眠る古老を知っていた。ローリー・キンギック。
アラスカのさまざまな村で、新しい時代に希望を託す次の世代が確実に生まれている。
******************************約束の川の旅~シーンジェック
![]()
アラスカ大学の博物館に飾られるミュリー夫妻の絵
![]()
ミュリー兄弟:
アラスカの伝説的な動物学者、ナチュラリスト、探検家、パイオニア。『マッキンレー山のオオカミ』の著者。
オーラス・ミュリーと妻のマーガレットがブルックス山脈を旅した時の姿が絵に描かれた。
未亡人となったマーガレットが書いた『Two in the Far North』は今もアラスカの古典。
ミチオと、シリア&ジニーは「いつか一緒に川下りをしよう」と約束してから何年も経っていた。
![]()
![]()
ワクワクしながら出発を待つ4人/焚き火でくつろぐシリア&ジニー
誰もが、それぞれの老いにいつか出会ってゆく。
それは、しんとした冬の夜、誰かがドアをたたくように訪れるものなのかもしれない。
年齢の差を超え、私たちが大切な友人同士だったのは、アラスカという土地を、同じ想いで見つめていたからだろう。
シリアとジニーは、ずっと遅れてこの土地にやってきたぼくに、何かを託すように語り続けてくれた。
そしてシーンジェックの旅は、ぼくが最初で最後に分かち合う、2人の物語になるような気がした。
夜が明ければ、シーンジェックの美しい流れが私たちを運んでゆく。
![]()
あとがき:ミチオとの旅~シリア・ハンター
アラスカのシーンジェック川をのんびりと旅した話の結末は、私たちの最良の友ホシノミチオが亡くなってしまったために、
残念ながら私が書くことになってしまいました。
ミチオと私たちの旅の目的の1つは、この地を訪れ、北極圏の野生生物保護に多大な貢献をした夫妻を讃えることにありました。
ミチオは、食事当番を決める段になると、頑として、それは自分がやるんだと譲りません。
自然の中を旅する時には、美味しいものをたっぷり食べたいんだ、だから食事のことは自分が計画をもって担当する、と宣言したのです。
私たちの旅は、のんびりとした、楽しいものでした。
(アラスカの人なら、こういうたびを「レイドバックな」旅と言うでしょう)
毎日、数時間、川をボートで行き、後の時間は岸に上がって周辺を探索してまわるのです。
ジーンと私は、今でも、あの不思議な旅のこと、そしてあのような素晴らしいプレゼントをしてくれた、穏やかで、思慮深い男のことを多い浮かべます。
自分のスピリットを自然界の鼓動に共鳴させていた男、それがミチオでした。
彼は大地と一体になり、そこに暮らす動物たちと一体になっていました。
ミチオのおかげで、私たちは、人間の生活とともにある野生の役割、そしてその存続が人間に必要であるということを、理解することができるのです。
1996年8月13日
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()





































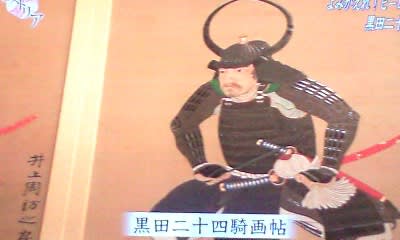






















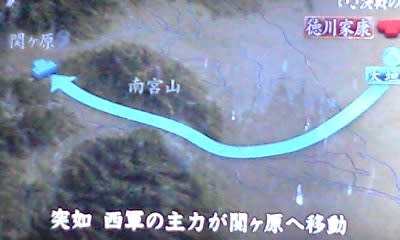









 )は、
)は、
 がトンネルに入って、灰島は急な発作にみまわれる。
がトンネルに入って、灰島は急な発作にみまわれる。 での通勤もムリ、飛行機
での通勤もムリ、飛行機 もムリ、狭くて暗い会議室もムリ、美容院でタオルをかけられても発作が出る(パニ障あるある
もムリ、狭くて暗い会議室もムリ、美容院でタオルをかけられても発作が出る(パニ障あるある 」
」 」
」
















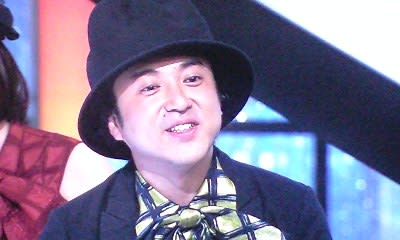
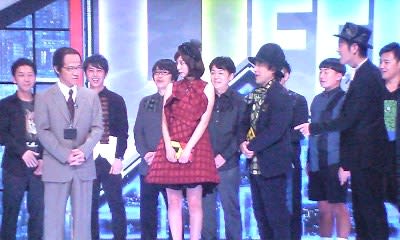
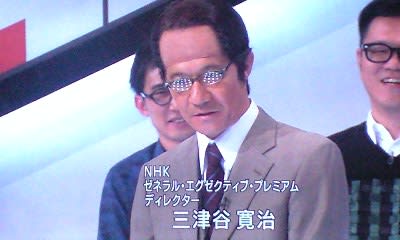
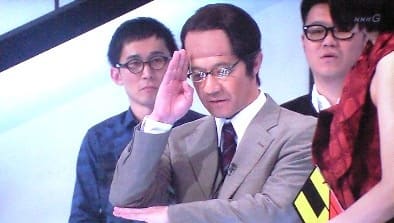
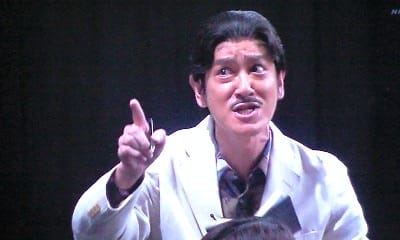
 )、彼らにつっこむゲスさんの部分とか見た。
)、彼らにつっこむゲスさんの部分とか見た。

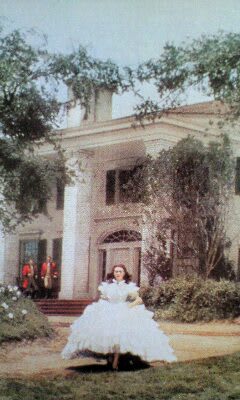














 の周りに立ち、“シャチがやって来た”という古いクランの歌がうたわれた。
の周りに立ち、“シャチがやって来た”という古いクランの歌がうたわれた。







 1917年 ジニー・ウッド産まれる@オレゴン州モロ
1917年 ジニー・ウッド産まれる@オレゴン州モロ






































 が失われ、それを大衆に知られないため、米副大統領は、地下にホテルが沈み、
が失われ、それを大衆に知られないため、米副大統領は、地下にホテルが沈み、

















 が聖書とされ、いつかヒトが戻って助けてくれると信じている。
が聖書とされ、いつかヒトが戻って助けてくれると信じている。


 はあるのか? 山は
はあるのか? 山は ? 河は
? 河は 、宇宙
、宇宙 すらも無限に重なり合っているという理論もあることだし。
すらも無限に重なり合っているという理論もあることだし。


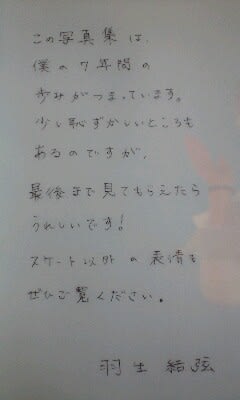


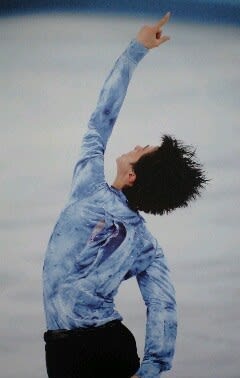






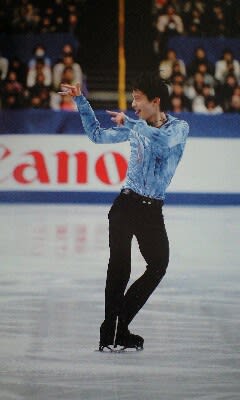
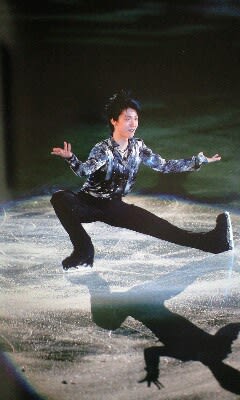



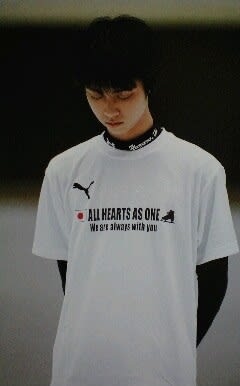
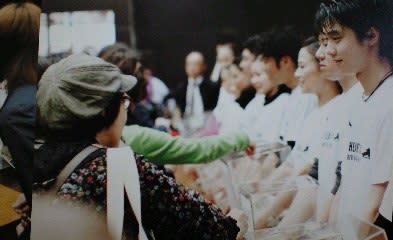







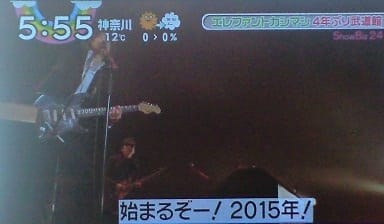
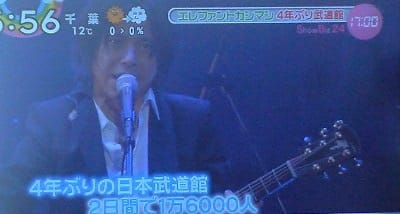

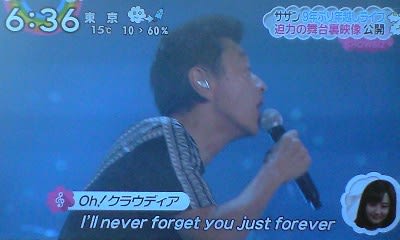



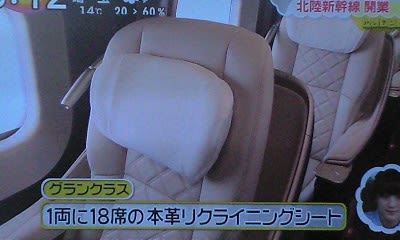


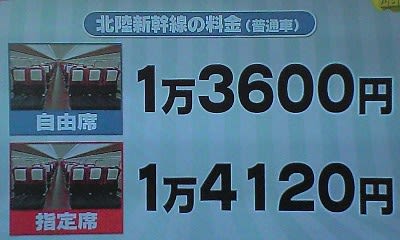
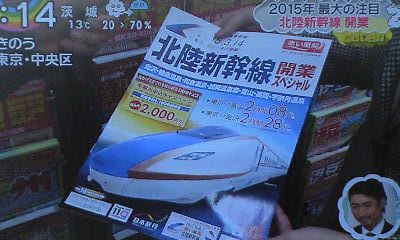

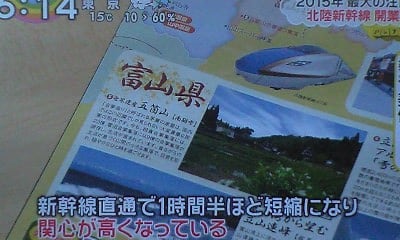





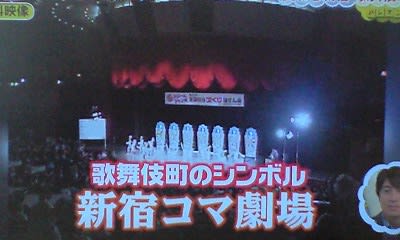

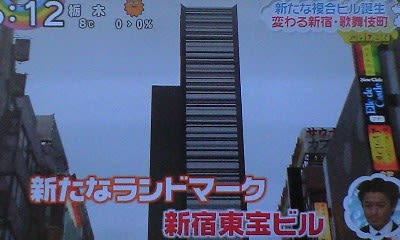
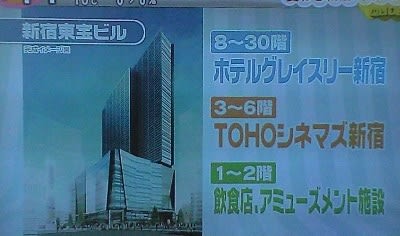


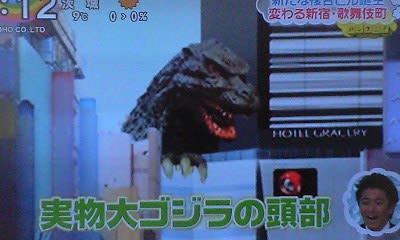


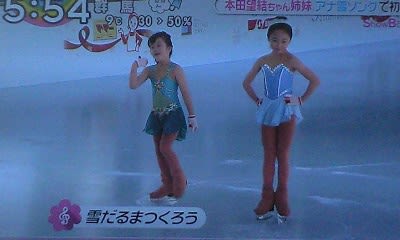

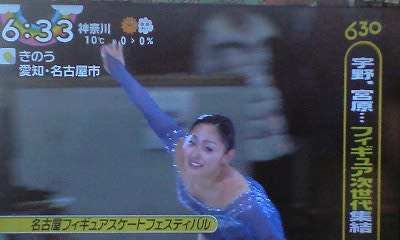

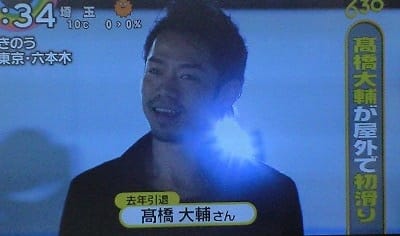


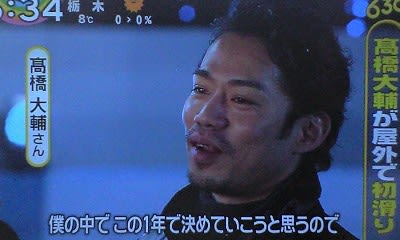
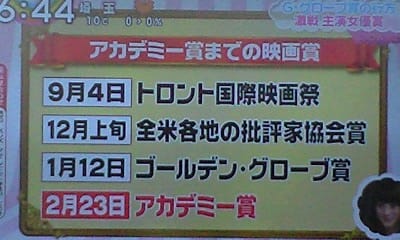
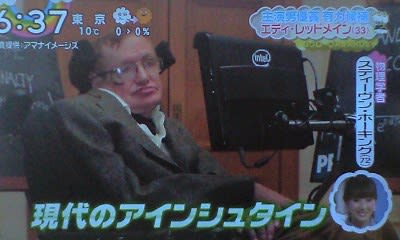










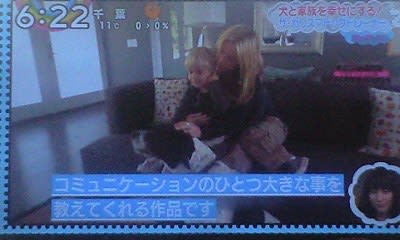
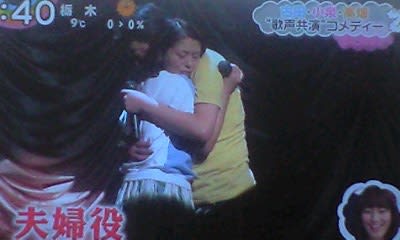
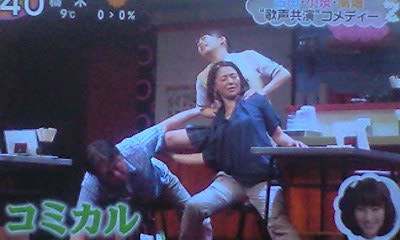







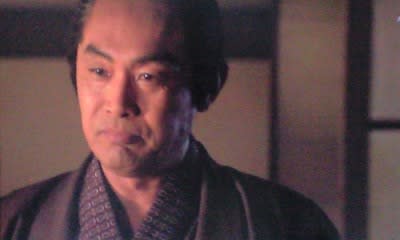






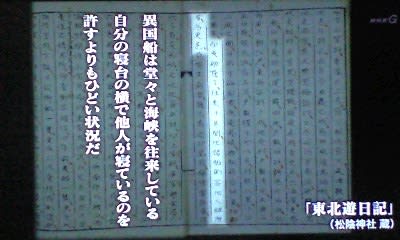
 が来ていることを知り憤ったという
が来ていることを知り憤ったという











